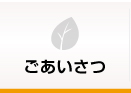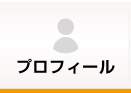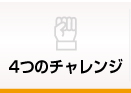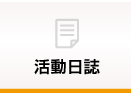第5期
2025年
2024年
第4期
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
第3期
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
第2期
2014年
2013年
2012年
2011年
第1期
2010年
2009年
2008年
2007年
府民文化常任委員会質疑
2024年11月28日
●スマートシニアライフ事業
公明党府議団の加治木一彦です。午前中の最後です。いましばらくお願いいたします。
それではまず、スマートシティ戦略部にお伺いをいたします。
同部の決算概要等報告書23ページ、スマートシニアライフ事業です。ほかの委員からも質問がございましたが、御勘弁ください。
我が会派は、このスマートシニアライフ事業につきまして、令和3(2021)年度のスタート時より、健康や暮らしなど多くの課題を抱えている高齢者こそ、デジタルの利便性を最大限受けるべきであるとして、デジタル技術の活用による高齢者の生活支援の重要性を訴えてまいりました。
これらの指摘を踏まえまして、公民連携で、タブレットやLINEを活用した実証を進めてこられた。私も、高齢者のQOL向上に資する取組として、これは大事なことだったと考えております。
特に、タブレット事業につきましては、国の交付金や企業版ふるさと納税の活用で、令和3(2021)年度から、高齢化率の高いニュータウンや都市部など様々なエリアで、タブレットをお貸しをして、民間企業と共に開発したポータルサイトのサービスを利用していただいておりました。
これまでのこのタブレット実証事業の成果と課題につきまして地域戦略推進課長にお聞きします。
スマートシニアライフ事業費のタブレット実証事業についてでございますが、国の交付金や企業版ふるさと納税による寄附金の活用により、高齢者のデジタルデバイドの緩和と生活の質の向上を図る取組として、令和4(2022)年2月からタブレット貸出しを実施し、実際の利用を通じてサービス改善に取り組んできたところでございます。
タブレット実証では、エリアの特徴等を踏まえ、3期にわたり実施し、第1期では、高齢化が進むニュータウンを中心に、堺市南区、河内長野市、大阪狭山市で実施し、第2期では、都市部の大阪市住吉区、東住吉区、生野区で、第3期では、スマートシティー化の取組を推進する大阪市阿倍野区、泉大津市で実施し、それぞれ延べ約850名、合わせて延べ約2500名に対し半年間の貸出しを行い、多くの高齢者にデジタルへの理解と便利さを体感いただいたところでございます。
また、利用者向けアンケートでは、終了後も引き続き利用したいと回答いただくなど、デジタルデバイド対策にも寄与する取組であると考えております。
一方、コンテンツの分野や事業の広がりの面で課題があったところでございますが、利用者ニーズの高い防災情報や行政サービス等を随時追加するなど、コンテンツの充実に取り組むとともに、令和4(2022)年12月より、LINEを通じたサービス、おおさか楽なびの提供を開始することで、一人でも多くの高齢者の皆様に御利用いただけるよう改善を図ってきたところでございます。
引き続き、府域で暮らす高齢者の皆様に、デジタルの利便性を身近に感じ、活用いただけるよう、実証事業の成果や課題を踏まえ、さらなる事業展開に生かしてまいります。
ありがとうございます。
私が以前、総務常任委員会に所属しておりました頃、ちょうどスマシ部も総務常任委員会の所管でございまして、過去2回、このスマートシニアライフ事業を取り上げたことがございます。
そのときに、改めて読み返したんですが、テレビ使えるぐらいの感覚でできるものにしてほしいいうてお話をさしてもろたことがあります。うちのおふくろは96になりました。あのとき94でしたが、今でもちゃんとテレビは自分でつけて見ております。これぐらいの感覚で使いこなせるぐらい身近なものに、また、使いやすいものになってほしいと願っております。
そしてまた、このスマートシニアライフ事業そのものは3年間の実証事業でしたので、もう終わったわけですが、その3年間で蓄えた様々なデータですとか、府民の皆様の御意見ですとか、民間企業さんの、いや、これはこうと、様々あるかと思います。こういうのを全部まとめて、これっきりで終わらせるのではなくて、次はどういう形で--やはり、府民の皆様に喜んでもらえるように。元気で生きている限り、いずれ私たちもシニア世代になっていくわけです。そのときに、あのときのスマートシニアライフ事業がこうやって便利なものにつながっているなというものになってほしいと、私もシニアの入り口にぼちぼち差しかかってきていますので、非常にそれを感じておりますので、お願いいたします。
2024年11月28日
●周遊促進事業
続きまして、府民文化部にお伺いいたします。
府民文化部の決算概要等報告書98ページ、周遊促進事業についてお伺いします。
周遊促進事業の取組の一つとして、お隣の兵庫県と連携し、地域の特色を生かした体験型の観光コンテンツを5件造成し、これらをつなぐテーマ別の広域周遊モデルコースを6件造成したとありました。
この取組は、単なる観光地巡りではなく、各地での魅力的な体験を通して大阪での満足度をさらに高める外国人旅行者向けの体験型観光の推進に向けたものであるとお聞きをしております。
この取組の具体的な内容、またその実績等につきまして、魅力づくり推進課長、お願いいたします。
体験型の観光コンテンツの造成につきましては、大阪・関西万博の開催を契機に、外国人旅行者の府内での滞在や周遊を一層促進するため、兵庫・大阪連携の一環といたしまして、市町村や旅行会社、施設等とも連携して、外国人旅行者に、大阪の歴史や文化、食などを体験し楽しんでいただけるよう、取組を進めているものでございます。
具体的には、食の専門ガイドと一緒に商店街を巡り、食材の買い付けと料理体験を行うツアーや、府内の歴史ある旅館に滞在し、生け花などの日本文化を体験するもの、府内にある世界的にも有名なフィギュアメーカーにおいて、アニメなどのフィギュアの塗装体験を行うものなど、地域の特色を生かした5つの体験型コンテンツの造成を行いました。
造成した体験型コンテンツについて、昨(2023)年度、旅行商品として試行的に販売を行ったところ、参加いただいた約40名からのアンケート結果では、約9割の方々から、家族や友人等へ推薦したいとの評価をいただきました。
今後、この結果も踏まえて、事業内容の改善等を行い、外国人旅行者に府内周遊を楽しんでいただけるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいります。
ちょうどこの質問をつくっているときに--公益財団法人日本交通公社というのは御存じでしょうか。こちらの柿島あかねさんという上席主任研究員さんが、まさにインバウンドに関して、消費促進における体験活動の活用可能性ということでレポートをまとめてはりました。
体験活動に関して、「1点目は、体験活動を実施することによって宿泊、飲食、移動等を伴うことが多いため、一人当たり旅行支出の増加に影響することが挙げられます」とまず指摘され、「2点目として、今後、成長の余地や可能性があることが挙げられます」とし、「3点目は地域資源の活用のしやすさです」と、その可能性を物すごく評価されています。
やはり、体験観光というのは、大阪市内に限らず、大阪府域各地でも様々な可能性があると思います。行かなければできないことをいかにうまく見つけて、それをインバウンドで来はるお客さんにアピールしていくか。ある意味、気持ちよくお金を使ってもらえる、これが物すごく大事やと思います。ぜひともこの取組を頑張っていただければと思います。
2024年11月28日
●大阪ミュージアム推進事業
続きまして、同じく決算概要等報告書98ページ、大阪ミュージアム推進事業についてお伺いいたします。こちらも既に何人かの方が質問として取り上げていらっしゃいますが、すいません、お願いします。
平成20(2008)年度のスタートから長く続いております。私が議員駆け出しのときから続いていまして、あっ、まだ頑張ってはったんやというのが正直な印象であるんですが、この個人や企業から頂く大阪ミュージアム基金への寄附を原資として、ずっと続けてこられております。これ自体、物すごく、最初のことを思い出したら非常にいい取組やったなと思うんです。自分たちのまちにこんないいものがある、それをどんどん知っていってもらおうということで、この大阪ミュージアムは私も非常にいい取組やと思っております。
今は、民間企業と連携した情報発信をしているとのことです。この取組は、連携によって事業費が抑えられるだけでなく、民間企業が持つ様々なノウハウ、ネットワークを活用することで、行政が単独で頑張るより、様々、効果的な事業展開ができるのではないかと感じております。
そこで、改めてですが、この大阪ミュージアム推進事業で実施をした民間企業との具体的な連携につきまして、こちらも、魅力づくり推進課長、お願いいたします。
令和5(2023)年度の大阪ミュージアム推進事業における民間企業等との連携実績につきましては、金融機関との連携では、店頭のサイネージや広報誌を活用した観光スポットやイベント情報の紹介を、大学との連携では、学生が府内の観光スポットを取材し学生目線で作成したレポートのホームページやSNSでの発信を、また大型の音楽イベント等では、大阪ミュージアムの取組を紹介するPRブースの設置など、様々な主体と連携した取組を実施したところでございます。
今後とも、本事業の充実を図るとともに、民間の力やネットワークも活用させていただき、あらゆる機会を捉えて大阪の魅力発信に取り組んでまいります。
16年たって、やっぱり大きく変わったのはSNSなんかなと。当時も既にインターネットによる発信というのがありましたが、これほど身近に手軽に誰でもできるというものではなかったと、16年前を振り返ったら思い出します。
先日、とあるテレビ番組で、京都の駅ビルのインスタグラムが取り上げられていました。最初は、何か、駅ビルのスタッフの皆さんでやっていた頃は、あんまり注目度もなかったそうなんですが、いつから始めたか、ちょっと見落とした、聞き損ねたんですが、大学生に駅ビルの魅力をアピールしてくださいと言って、インスタグラムの宣伝をお任せしたら、あっという間にフォロワーが増えまして、先ほど見たら3万5000人いてはるそうです。びっくりしました。
16年前でしたら、映像を撮るというのはかなり手間やったと思います。それこそハンディーカムみたいのを持って、編集するのも結構大きい機材が要ったと思うんですが、もう、それこそスマホ一つで撮って、編集もして、字幕もつけて流せる、こんな手軽な時代になってんねやなと改めて感じた次第です。
この大阪ミュージアムに関しましても、ここの中でも、学生さんとの連携ですとか企業さんとの連携とか、様々ございます。始まったときに比べたら、発信のハードルというのはぐっと低くなっていると思います。せっかく、いいもの、コンテンツは持っています。これをもっともっとうまく発信をしていっていただければと思いますので、お願いいたします。
2024年11月28日
●大阪文化資源魅力向上事業
続きまして、大阪文化資源魅力向上事業。決算概要等報告書106ページの文化振興事業のうち、大阪文化資源魅力向上事業について伺います。
この事業は、地域の魅力発信を目的として、昨(2023)年の10月から今(2024)年の3月までの間、府内各地の神社仏閣等の文化財を舞台に、伝統芸能や音楽、アートなど、複合的な文化芸術プログラムを展開してきたものであります。
大阪府域には、府民でさえ知らないような魅力的な文化資源が数多くあり、それらを活用しながら、この文化芸術プログラムを実施していくということは、多くの皆様に大阪の魅力を伝えることができるものやと考えます。
この事業は、令和5(2023)年度から7(2025)年度までの3か年の事業やとお聞きをしておりますが、令和5(2023)年度の事業の振り返り、そしてまた、これを踏まえて、今(2024)年度の取組にどのようにつなげておられるのか、こちらは、文化課長、お願いいたします。
大阪文化資源魅力向上事業では、令和5(2023)年度、府内を5つのエリアに分けまして、北摂エリアでは、豊中市にある木造和風教会で古楽器を使ったバロックコンサートを、北河内エリアでは、枚方宿にある江戸時代の趣を残す旧鍵屋旅館での華道と雅楽のパフォーマンスを、中河内エリアでは、東大阪市にある古民家におきまして町工場で制作されたファクトリーアートの展示とジャズの公演を、南河内エリアでは、楠公誕生地で楠木正成にちなんだ講談をはじめとした上方演芸を、泉州エリアでは、国指定名勝である岸和田城の八陣の庭での光のアートインスタレーションを展開し、多くの方に御来場いただきました。
来場者からは、イベントをきっかけに、ふだん訪れることのない文化財に接することができた、文化財の歴史や背景などを知ることができた、文化芸術に気軽に触れることができたなどの感想をいただいております。
今(2024)年度は、昨年度の成果を踏まえまして、多くの方に文化資源の魅力を発信できるよう、市町村や地元の文化芸術団体のイベントとより連携できる開催時期や場所を選定しているところでございます。
加えまして、文化芸術に携わる専門家をプロデューサーとして活用することを本格化し、文化芸術プログラムをより魅力的な企画にするとともに、地域における持続的な取組につながるよう、人的ネットワークやノウハウの共有など、地元との連携を強化しております。
今後も、文化資源のさらなる魅力向上と地域の魅力発信につながるよう、しっかりと取り組んでまいります。
重ねてになりますが、大阪にはすばらしいもんがいっぱいある。こちらの委員会の所管ではないですが、日本遺産という取組、皆さん、御記憶あろうかと思います。私も何回か議会で取り上げたことがございます。
で、大阪にあるので、実際に見に行かんとあかんと思いまして、河内長野の観心寺ですとか富田林の寺内町ですとか--うち、大阪市淀川区ですんで、なかなか南のほうって目が行かへん、行きにくいとこやったんですが、そういうのがあって、実際に出向いていって、あっ、すごいものがあるというのを感じた次第です。
やはり、大阪に住む私たちが、大阪にこんなええもんあるんやでというのを知っていることで、またいろんな大阪に訪れてくれはる、それこそ国内外から来てくれはるお客さんに対しても、いいおもてなしができる、いい宣伝ができるもんやと感じておりますので、こちらも、引き続き、アピールのほど、お願いいたします。
2024年11月28日
●国際会議場管理運営事業
それでは最後に、国際会議場につきましてお伺いいたします。決算概要等報告書166ページに記載の国際会議場管理運営事業についてお聞きをいたします。
令和5(2023)年度は、35億円を超える額が支出されております。行政コスト計算書を見ますと、その大部分は維持補修費とされております。
大阪府立国際会議場は、平成12(2000)年の開業以来25年が経過しようとしております。MICE施設として必要な機能を維持し、利用者にとって魅力的な施設であり続けるためには、維持補修というのは当然不可欠やと考えております。
令和5(2023)年度のこの補修事業の内容につきまして、こちらは、都市魅力創造局副理事、お願いいたします。
大阪国際会議場は、最近では、令和元(2019)年6月にG20大阪サミット2019シェルパ会議の会場となり、また、令和5(2023)年10月にはG7大阪・堺貿易大臣会合の主要会場となるなど、国際水準の会議環境を提供するMICE施設としての役割を果たしております。
令和5(2023)年度は、工事請負費として28億1416万余円を支出しており、これは、主に、調光照明、音響設備及び舞台幕を昇降させるための設備など、比較的大きな規模の工事を実施したものでございます。
大阪国際会議場の補修工事に際しましては、国際会議やコンサートなど、その用途や利用者のニーズを踏まえた機能や環境を十分に提供できるよう、施設の状況を最も把握している指定管理者などとの協議の下、安全や緊急性などの観点から優先順位をつけて、順次実施しているところでございます。
MICE施設に欠かせない音響設備などは、技術の向上もあるかと思います。当然、その時代時代に合ったものに更新していくものであります。利用者に選んでもらえる施設であるためにも、引き続き、適切な維持管理、またその更新をお願いいたします。
続きまして、記載されております国際会議場における国際会議成約件数につきまして伺います。
目標値の43件に対して実績値が105件、随分頑張らはったなと思います。この理由や背景につきまして、都市魅力創造局副理事、お願いいたします。
国際会議成約件数の年度目標を設定しました令和5(2023)年度当初には、新型コロナウイルス感染症による影響が残っておりましたが、その後、5月に5類感染症へ移行されたことにより、大型会議の対面開催の動きが戻ってきたことが、想定よりも多くの成約をいただいた要因と考えております。
また、令和6(2024)年4月より利用料金改定を行いましたが、令和5(2023)年度中に成約した案件は旧料金の適用としたため、令和6(2024)年度以降の利用を検討中であった案件が前倒しで成約されたことも、令和5(2023)年度の目標を上回った要因の一つと考えております。
そうですね、国際会議が43件に対して105件ということで、いろんなものがあったかと思います。単純に件数も大事なんですが、どんな会議、イベントを開いてもらえるかというのも大事なんかなと思います。
この国際会議場と直接関係するわけではない--だけでできる話ではないですが、例えば、大阪では2019年6月にはG20大阪サミットってありました。このときに大阪ブルー・オーシャン・ビジョンというのができまして、外務省のホームページを見ましたら、87の国と地域がこのブルー・オーシャン・ビジョンを共有するということを表明してくれてはる。そうすると、少なくとも、その国、地域に対しては、大阪ブルー・オーシャン・ビジョンということで、大阪という名前が残るわけです。
国際会議、国際的なイベントをやることで、大阪という名前のついた何がしか、そういう遺産、レガシーを残していく、こういったことも、これから先、大事になってくるんやないかなと感じております。これはもちろん国際会議場単独でできる話じゃありません。大阪全体で考えてやることやと思いますので、大阪の魅力づくりという観点からも、この国際会議、物すごく大事な要素でございますので、引き続きよろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。