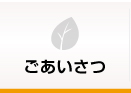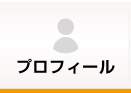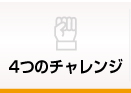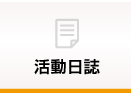第5期
2025年
2024年
第4期
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
第3期
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
第2期
2014年
2013年
2012年
2011年
第1期
2010年
2009年
2008年
2007年
関西広域連合議会一般質問
2024年8月22日
●大阪・関西万博を契機とした域内市町村の国際交流の推進
公明党大阪府議会議員団の加治木一彦です。議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、順次質問を進めてまいります。
まず、大阪・関西万博を契機とした域内市町村の国際交流の推進について伺います。
内閣官房が全国向けに地域住民と万博参加国・地域の関係者が地方自治体の事業を通し国際交流を続けていくための枠組み、万博国際交流プログラムを実施しております。これまでに全国で54自治体のプログラムが登録されています。国は、登録自治体が実施する参加国・地域との相互理解や国際交流を通した地域の課題解決、活性化などを支援するとしています。私は、主に事業の対象となる基礎自治体が当該プログラムに積極的に手を挙げ、地域住民と万博参加国・地域の関係者の交流をより盛んにすべきと考えています。
今から6年前、2005年の愛・地球博の当時に愛知県知事だった神田真秋氏にお話を伺いました。興味を引いたのは、一市町村一国フレンドシップ事業です。当時、県内にあった86市町村が、それぞれ万博参加国と交流するというものです。神田氏が訪れた2000年のドイツ・ハノーバー万博で、特定の参加国にスポットを当てるナショナルデーのイベントがあまりに注目されていなかったことから、万博が始まるまでに各国と絆をつくればいいと思いついたそうです。
当時の新聞記事をひもとくと、交流相手国のナショナルデー当日に、人口1,400人の村から300人が万博会場に駆けつけた。幼稚園児が相手国の愛唱歌に合わせてダンスを披露した。小・中学校の給食に相手国の料理が出たなど多種多様で、楽しい取組にあふれていました。グローバル化や情報技術の発展がこれほど進んだ時代に万博は必要なのか、この問いに神田氏は、世界の人が一つの場所に集い、互いの価値観に触れ合う意味は大きいと答えています。今回の万博開催地、大阪・関西も心すべきことだと感じています。
今回の万博国際交流プログラムは、(2024年)9月末が登録申請の締切です。大阪府内の市町村は数多く手を挙げていますが、連合域内に目を向けるとまだまだ余地がありそうです。関西広域連合として、域内市町村に万博国際交流プログラムの意義や目的、メリットなどを広く周知し、多くの基礎自治体の国際交流を大いに後押ししてはいかがでしょうか、御所見を伺います。
お答えいたします。
大阪・関西万博に多くの国が参加することを契機に、全国各地域で地域住民と万博参加国の関係者が地方公共団体の事業を通じて国際交流を図ることは、相互理解や誘客を促す観点から非常に有意義だと考えます。関西広域連合といたしましても、交流人口の拡大を図るため、関西経済界や博覧会協会と共に、国に対し、万博参加国との交流促進に取り組む自治体への財政支援を要望してきたところでございます。
万博国際交流プログラムにつきましては、(2024年)7月末時点で、広域連合域内の28の自治体が登録をされております。このうち、8か国と交流する大阪府では、相手国の留学生と高校生が共通のテーマとして、例えば環境やSDGsのような社会課題を取り上げ、解決に向けた意見交換などを通じて、相互理解を深める取組が行われると伺っております。関西広域連合といたしましても、連合域内から一つでも多くの市町村が万博国際交流プログラムに参加し、活発な国際交流がなされるよう促してまいりたいと存じます。
2024年8月22日
●関西パビリオンにおける子どもの参加
次に、関西パビリオンにおける子どもの参加について伺います。
関西広域連合として、大阪・関西万博にパビリオンを出展します。テーマは「いのち輝く関西悠久の歴史と現在」、まさに来訪者に関西の悠久の歴史と現在を感じてもらい、未来の姿を描いてもらいたいとの願いを込めているとお聞きしております。関西パビリオンは、参加各府県の創意工夫の下、各地域の生活環境、地域産業、観光、文化等の魅力を体現し、国内外の人たちにその魅力を味わってもらう。さらに、関西各地へ実際に足を運んでもらうゲートウエーとなるパビリオンを目指しています。私も完成を楽しみにしております。
特に未来を担う子どもたちが大阪・関西万博を訪れ、最先端の技術やサービス等に直接触れることで、大いに興味、関心を高めてくれることが重要と考えます。その一環として、万博への修学旅行や校外学習といった教育旅行は有意義なもので、構成府県市がそれぞれ実施に向けて取り組まれています。さらに私は、子どもたちが関西パビリオンを訪れるだけでなく、一緒に参加できるパビリオンにすべきと考えています。例えば、関西パビリオンの一日館長や、子どもたちにSDGsをテーマに課題研究をしてもらい、優秀作品に対し、パビリオンで表彰式をする、発表の機会を設けるなどしてはいかがでしょうか。子どもたちにとってもよい学習目標になると考えます。御所見を伺います。
お答えいたします。
「未来社会の実験場」をコンセプトに開催され、国内外の様々な文化や技術に触れることのできる大阪・関西万博は、子どもたちにとって、自分の将来を考えるきっかけとなるものであり、一人でも多くの子どもたちが来場されることを期待しています。
パビリオンでの参加体験は、子どもの主体的な学びや創造的な行動を促す機会として、有意義なものと認識しておりまして、関西パビリオンにおきましては、参加府県の創意工夫の下、来館者が「関西悠久の歴史と現在」や「未来社会のデザイン」を見て、触れて、感じることができる体験型のパビリオンを目指しているところです。また、子どもたちを含む参加型の試みとして、関西パビリオンで上映する動画やイラストを公募するなど、誰もが主体的に参加できる展示企画を予定しております。
今後は、出展府県とも連携いたしまして、例示いただきました子どもたちによる一日館長ですとか、アイデア発表などの企画も参考にしながら、参加体験を通じ、子どもたちの学びにつながるような工夫を凝らした取組を検討してまいりたいと存じます。
ありがとうございます。
私、大阪ですので、1970年万博に行かれた方のお話をよく聞くんですが、本当に鮮明に覚えてらして、あんな楽しいことはなかったと。ぜひとも来年2025年万博も見に行った人が、それこそ30年、50年たっても、あんな楽しいことはなかったと。それはまさに、子どもたちにどれだけ夢を持ってもらえるか、そしてまた、それを実現してもらえるか、そこにかかってくると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
2024年8月22日
●淀川舟運を生かしたにぎわいづくり
次に、淀川舟運を生かしたにぎわいづくりについて伺います。
淀川流域で現在、大阪・関西万博開催までの完成を目指し、大阪市東淀川区と都島区にまたがる淀川大堰閘門、私の地元、大阪市淀川区の十三地区や京都市伏見区の伏見地区で船着場の整備が進んでいます。完成すれば、大阪湾から京都への船の往来が可能となります。船での移動は、陸路に比べ時間がかかるものの、非日常感を味わえる貴重なものです。見慣れた風景も視点を変えることで魅力が増すようにも感じます。水都大阪をはじめ、淀川流域の魅力を世界に発信できる絶好の機会として、淀川舟運の活性化に大いに期待しています。
令和4(2022)年3月、淀川舟運活性化協議会が発足し、国や流域自治体、民間が一体となって活性化に向けた取組がされていると承知しております。この協議会には、関西広域連合の構成府県市の大阪府、京都府、大阪市、京都市が参画しています。それぞれに活性化に向けたイベントをされていますが、さらなるにぎわいづくりに向け、複数の流域自治体が連携し、相乗効果を高める工夫が必要と考えます。
例えば、春の桜の咲く時期には、大阪市内の大川さくらクルーズ、京都府八幡市の背割堤周辺の宇治川を行くさくらであいクルーズ、京都市伏見区の宇治川派流を行く伏見十石舟があります。琵琶湖疏水流域にまで目を向ければ、京都市左京区の岡崎さくら回廊十石舟めぐり、京都市東山区と滋賀県大津市を結ぶびわ湖疏水船があります。このびわ湖疏水船、キャンセル待ちが出るほどの大人気とお聞きしております。いずれも、これまでに私が乗船したり、就航している様子を実際に目にしたりしております。乗客の皆さんが楽しんでいる姿に観光集客のさらなる可能性を感じております。
複数の流域自治体が構成府県市となっている関西広域連合として、淀川舟運を生かしたにぎわいづくりを促進するイベントは非常に有益ではないかと考えます。御所見を伺います。
淀川舟運を生かしたにぎわいづくりについてでございます。
大阪と京都を結ぶ水上交通路として活用されました淀川舟運は、関西の文化を形づくってきた魅力の一つであり、観光誘客の観点から、沿川の自治体が連携して広域に取り組むことは大変効果的だと考えております。
そのため、議員から御紹介ありました淀川舟運活性化協議会では、淀川沿いの府県市が参画して淀川舟運を生かしたにぎわいづくりに取り組んでおりますが、万博開幕の6か月前となります10月13日には、大阪から伏見まで、一気通貫の航路で船が運航されるとともに、国や沿川自治体、民間事業者が連携して、舟運を契機とした広域的なイベントが実施される予定でございます。また、昨(2023)年3月に構成府県市や民間企業などと共に設立いたしましたEXPO2025関西観光推進協議会では、沿川の歴史、文化のコンテンツや淀川舟運を活用した旅行商品の造成に取り組んでいるところでございます。
広域連合といたしましては、万博開催期間中に万博会場から京都までの船旅の船内で、例えば関西の歴史、文化を学び、特産品を楽しむイベントを開催するなど、関西の魅力を十分堪能いただける取組も検討してまいりたいと考えております。さらには、大阪・関西万博の終了後も、国や沿川自治体、さらにはできる限り多くの主体と連携をいたしまして、淀川舟運を生かした効果的な観光誘客にも取り組んでまいりたいと考えております。
2024年8月22日
●ツーリストシップの普及
最後に、ツーリストシップの普及について伺います。
ツーリストシップという言葉、初めてお聞きになった方もいらっしゃるでしょう。京都市に拠点を置く同じ名前の一般社団法人が提唱している考え方です。旅先に配慮したり、貢献しながら、交流を楽しむ姿勢やその行動と定義しています。スポーツマンシップから着想を得て、ツーリスト、旅行者に接尾詞のシップをつけた造語です。
コロナ禍が明け、日本を訪れる外国人旅行者が増え続けています。日本政府観光局が昨日公表した今(2024)年7月の訪日外国人数は、推計値で329万2,500人と、2か月連続して単月で過去最高を記録。7月までの累計でも2,106万9,900人と過去最速で2,000万人を突破しました。
私もふだん、大阪のまちを移動していると、世界のいろんな言葉を耳にします。これほど急回復するとは想像もしていませんでした。訪日外国人旅行者が増えることは、日本国内の経済活動や地域の活性化に恩恵がある一方、私有地への無断立入りやごみのポイ捨て、公共物への落書き被害、公共交通機関の混雑など、負の側面も目立ってきています。私はより多くの自治体がツーリストシップの考え方を取り入れたマナー啓発をしていくべきだと考えます。
先日、京都市営バスに乗車した折、交通局ニュースとして、このツーリストシップを啓発する車内広告物を目にしました。関西広域連合の域内には、魅力ある観光地が数多くあります。観光客が増えることでの負の側面に頭を悩ませる事例も増えてきているのではないかと危惧しています。旅行者向けのマナーの啓発活動は広域で取り組むほうがより効果的だと考えます。関西広域連合として、ツーリストシップを率先して提唱し、構成府県市内で普及させていくべきと考えます。御所見を伺います。
ツーリストシップの普及についてでございます。
観光需要の急激な回復に伴いまして、一部の地域におきましては、外国人観光客によりますごみのポイ捨てや落書きなど、マナーの問題が生じております。これらに対処する手法として、議員から御紹介のございました旅先への配慮や旅先への貢献を意味するツーリストシップという取組が注目を集めております。このツーリストシップは、京都の大学生が、先ほど御紹介ありましたように、スポーツマンシップから着想を得て考案した造語であると伺っております。現在は、一般社団法人ツーリストシップが設立され、例えば、各地の観光地で旅先クイズ大会を実施されるなど、観光客に分かりやすい内容や表現でツーリストシップの普及啓発に取り組んでおられます。
関西広域連合といたしましても、外国人観光客に住民生活に配慮し、地域の文化や習慣を理解していただく活動は、持続可能な観光を推進するために大変重要であると考えておりますので、現在進めております関西観光・文化振興計画の中にこれも盛り込んでいくことを検討してまいりたいと考えております。
このツーリストシップに関しまして、8月6日の日に、第3回のツーリストシップサミットというものが大阪市内で行われました。結構、各地からいらっしゃって、このツーリストシップ、私たちも取り組みますということで、広がりを見せてきております。発祥の地がこの京都であり、また関西ですので、乗り遅れないように、しっかりと取り組んでいただければと思います。
以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。