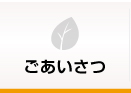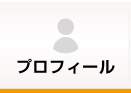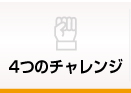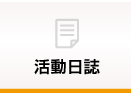第5期
2025年
2024年
第4期
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
第3期
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
第2期
2014年
2013年
2012年
2011年
第1期
2010年
2009年
2008年
2007年
府民文化常任委員会 参考人招致
質問事項
2024年10月31日
●宿泊税
公明党府議団の加治木と申します。庄司先生、今日は東京から大阪まで、ありがとうございます。
先ほど、先生の勤めていらっしゃる立教大学観光学部の入学案内を読ませてもらいました。私が高校3年生やったらここ行きたいなと思うような、めっちゃ魅力的な学部やなということで、非常にすごいこと、これを日本で初めて取り組まれてきたということもすごくの敬意を表する次第でございます。
先ほどの先生の御発言の中で、レベニュー・マネジメント、それをやることで、観光の何というんでしょうか、ある意味オーバーツーリズムみたいなものを解消するならそういうやり方があるということで、先生も御存じだと思いますが、ギリシャがまさにクルーズ客税ということで、こういうことをやるということで国として方針を決めて動き出していると。
今の日本で、まして大阪でそこまでやる必要があるかというような、私も疑問なんですが、もし日本でやるとしたら、例えばどういった時期に、どういった地域がこういった手法を取り入れたら効果的なのか、先生、お考えがありましたらお聞かせください。
御質問、ありがとうございます。
まさに丁寧な説明ということが間違いなく必要なんだろうなというふうに思います。また、先ほど申し上げたように、それが観光振興のためという、ある種狭い視点ですと、なかなか理解が得られないかなというふうに思います。観光客も楽しみに来ている、そもそもの日本の資源、あるいはそういうものを守る、そしてそれがサステーナブル、継続可能であるというところがポイントだと思いますので、そこは丁寧に御説明いただく必要があると思うのですが。
その観点からいいますと、やはり今ですと自然環境のようなところに対するダメージの問題、そして、それが文化、食文化なんかもそうかもしれませんが、あるいは先ほどのお祭りというような、そういった文化史的な資源の保全に関与するようなこと。そして、そもそもが地域から人口が減少しているというようなことがございますので、地域社会そのものが活性化する、継続できる、それぐらいの3つぐらいの段階、カテゴリーがありそうかなというふうには思っていますけれども、今ですと、僕の今の肌感覚では、特に自然環境破壊、自然環境保護に関することというのは、多分相当程度に理解が得られるのではないかなと思います。
これは、例えばごみの問題ですとか、あるいはフードロスですね。観光客が増えることでのそういったいわゆる自然環境に代表されるようなものに対する弊害、そこにまず、少し抑制という意味でも税金をかける。そしてそこでの税収がそういったことに使われるという領域は、理解が得られやすい領域かなというふうに私自身は思います。
もう一つまたお聞きしますが、ギリシャの事例ですと、まさにクルーズ船ですので、多分、クルーズ船が港に着きました、着いた時点で誰が来たかが特定できる、何人来たかが分かる。じゃ、すいません、お幾らくださいということで、非常に分かりやすいと思うんですが、大阪のまちの場合、宿泊税はホテルが、すいません、皆さんからくださいということで納めていただいていますが、今知事が考えているような、外国人旅行者だけからお金を取るというやり方をしようとした場合に、ちょっとどういう手法が可能なのか、私は思いつかないんですが、先生、こういうことやったら可能になるのではないかということがもしございましたら、お聞かせいただけますでしょうか。
なかなか難しい御質問をいただいてしまったなというふうに思うのですが。
まずは、直接お答えする前に、全くおっしゃるとおりだと思います。御懸念はそのとおりで、我々の業界でよく知られている事例としましては、アメリカのナショナルパークです。アメリカのナショナルパークは、もともと国有地だったところを公園にしておりますので、門が閉まるんです。ですので、確実に入ってくる方から入場料を取れるので、あのナショナルパークというやつが非常に上手に運営できているということが分かっております。
先ほどの僕の話にもありましたけど、日本の場合、国立公園法は、既に人が住んでいらっしゃるところに後から網をかけているので、それこそおっしゃるとおり、入り口、出口はあってないようなものというのが、今でいう環境省さんがずっとここ困っておられる問題ですので、そういう意味での御懸念点は共有しているつもりです。
ちょっと僕はそれほど詳しいわけではないのですが、いわゆるIT、デジタル系の会社さん、例えばNTTデータさんというようなところと私はいろいろ情報交換をしているのですが、そういった会社さんがやはり今、様々な形でそういうものを追跡できるというようなことをされておりますので、例えば入国の段階で何らかの登録をしてもらうなりというようなことで追跡することは、それが理解が得られるかどうかということは問題があるかとは思いますけれども、現状でかなりの程度それを把握することは技術的には可能だというふうに僕自身は聞いております。例えば携帯電話一つ取っても、その段階で追えることは追えますよね。ただ、その辺がどういうふうに理解が得られるかということと、あともう一つは、実際にそれにかかる手間暇というようなことがあると思います。
もう一つは、これはアイデアというか案としてですけども、日本ではほとんどこの事例がないというふうに僕は思っているのですが、ヨーロッパの方々なんかは、あんまり細かくチェックしなくて、違反が見つかったときだけ罰金を科すというやり方をされますよね。ですから、僕も随分前にドイツに行ったときに、高速道路の料金所がないんですよね。ステッカーを買って車に貼れと言われるわけです。それが1年間分とかを払って、みんなが貼っていればいい。比較的見えやすいので、それで通行していいよと。もしそれが違反しているのが見つかると、大変な金額の罰金額というふうにして、毎回チェックするということではなくてというふうにしてというやり方が、僕の感じだと比較的ヨーロッパの方々は好きですけど、日本はどうも何か毎回ちゃんと取ろうという、チェックすることのほうがお好きなようなので。まあ一つの案としては、御検討いただく分にはそういったやり方もあるというふうに一応御紹介をさせていただこうと思います。
ありがとうございます。今の先生の話をお聞きしていまして、私も旅行が大好きで、若い頃はバックパックをしょってあちこち行ったものですから、まさにヨーロッパの電車で、私は一日乗車券を買って乗ることがほとんどやったんですけど、言わはるとおり、たまたま係員の人が乗ってきて、運悪く持ってへんかった人がしょっぴいていかれた場面を何回か目にしたことがあります。
確かにやり方一つというのはあるのかなというのが一つと、これはもう全く私の個人的な意見なんですが、外国人旅行者だけに狙い撃ちしてお金を取るというのは、大阪のまちは外国人に来てほしくないのかというようなメッセージを与えてしまいかねない。そこは先生もおっしゃっていたとおり、どう理解を求めるか、また私たちがふだん払っている税金でしたら、これがこう回って返ってくる、受益もこちらに返ってきますが、外国人旅行者の方からお金を取った場合、その方が二度と来ない人かもしれないじゃないですか。昔に来た人の分で今の自分が助かっているというのはあるにしても、今まで自分の分が次の人に役に立つという理屈が果たして理解してもらえるのかということもあるかと思います。
ですので、外国人徴収金というのは考え方として面白いと思うんですが、なかなか難しいんじゃないかなということを感じております。
それと、がらっと論点は変わるんですが、恐らく先生もこれを御覧になったんやと思います、この東京都の。大阪の場合、大阪府が大阪府域全体で宿泊税を頂いてやっていますね。福岡でしたら福岡県と福岡市、北九州市がそれで分けて取っていたりすると。こうなったら、東京都もそうですけど、広域自治体としてこの宿泊税を運用する場合、特定の地域ということで、実際上がってくるお金は多分大阪市域から来るのが一番多いと思うんですが、大阪府が頂いている以上、府域全体に目を行き渡らせるように、また、府民の皆さんに喜んでもらうような使い方をすべきやないかと考えますが、先生が御存じの中で、上手な使い方をしている、もしくは、こういう観点で使っているのがいいのではないのかということがありましたら、お聞かせいただけますでしょうか。
まず、前半の部分のお話なんですけれども、確かに外国人というときに非常に難しいものがあると思っています。もう一点だけ明確に指摘をしておいたほうがいいのかなと思ったのは、外国人だから、あるいは外国籍だからということではなく、つまり、外国籍の方でも居住しておられる方、働いておられる方というのは当然除外するという考え方はあり得ると思っています。外国の、いわゆる観光客として来られている方。ですから、もしかすると、そういうケースはあるんでしたっけ、日本国籍だけれど国内で税金を払っておられない方については、遊びに来られたときには外国人観光客扱いということだって考え方としてはできるというふうに思います。
これは、そのお金がどこに使われているかということはもちろん重要なんですけれども、少なくとも現状の観光的な価値がある資源をつくったり守ったり維持するための資金を負担しているかどうかということだけだろうと思います。こちらにつきましては、多分参考になるのが、例えばアメリカなんかで州立大学に行くときに、州の子どもの授業料と州以外から来る学生の授業料は大幅に違うというようなことは既に理解をされるわけですので、それに準じた形でいけるかなというふうに思っております。
ごめんなさい、二つ目の……。
すいません、いっぱいしゃべりましたので。失礼いたしました。宿泊税の使い方として、これはいい使い方をしているのではないかというところがありましたらということです。
国内での事例が限られていることもあるので、自分はちょっと海外を考えているのですが、やはりここは正直申し上げて非常に難しい課題だというふうに思います。
特に今、日本ではDMO(観光まちづくり法人)だとかDMC(観光まちづくり企業=仮=)さんが広域連携というようなことを盛んにおっしゃって始めているのですが、なかなか解決しない根本的な問題の一つがここに実はあると思っています。
といいますのは、我々、自分が観光するときは、当然自分の家から目的地に行って、あるいは帰ってくる。その途中で、例えば昼御飯を食べたりとか、先ほどの話で土産物を買ったりとか。当然それがあって、僕はこれをトータルバリューと最近呼ぶんですけど、3日間なら3日間全体でどれだけ楽しんだかということで、この観光の価値を僕たちは決めているんですけど、でも、残念ながら、途中で昼御飯を食べるだとか、途中で買物するところとこの目的地は全然連携していないのでという御趣旨の御質問だと思うんです。
それは全くそのとおりで、ですから、そこはもしかすると、今後、先ほどのお話とつながるかもしれませんが、誰がどのように移動しているのかということがデータとしてもう少し取れるようになってくると、その間で上手にそれを分配しましょうよとか、自分たちにとって重要なパートナーとなっている地域がどこなのかというようなことが見えてくると、そことシェアするというような議論が出てくると面白いなと私自身は思っていますが、ちょっとまだまだ難しい問題だというふうに思っております。
今の先生から御指摘あった、日本に住んでいない、また外国で税金を払っている日本人から取るというのは、確かに面白い。こちらは全然思いつかなかったものですから。逆に言って、先生も御存じのように、ジャパン・レール・パスって、日本国籍の人でも外国に住んでいたらそれを買って使えますよね。それでアメリカ在住の友人がいつだか来て、遊んで帰ったものですから、いいなと思ったんですが。
最後に一点、まさに先生の専門分野にもなるんですが、宿泊税の使い道として、観光人材の育成--観光人材は幅広いんですけど--観光人材の育成という使い方もあっていいかと思うんです。もしこれを大阪府がやるとしたら、どういった方面にお金をかけるべきやないかというのがもしございましたら、お聞かせください。
人材育成につきましては、まさにそのとおりだというふうに思います。大阪でももう今大きな流れになっていると思いますが、特に宿泊に関しては、ホテルを運営するというふうに僕らは呼ぶんですけど、ホテルを運営する人たちと、それからホテルがある土地とか建物を所有する人たち、オーナーと言ったりしますが、その人たちが分かれる、別の人になるという現象が知られています。これがもう実は1990年代にアメリカからスタートして、世界中にあっという間に広まりました。御当地ですと、近鉄さんが、2021年3月ぐらいでしたっけ、ブラックストーンというファンド会社に8ホテルぐらいを売却したというのが大きなニュースになったかと思います。あれも特に東京なんかだと誤解して伝わっているんですけども、近鉄さんがホテルをやめたわけではないんですよね、あれ。近鉄さんが持っておられるホテルの建物と土地をブラックストーンというところに売却をする。つまりは、ホテル業というのは、オペレーターと言われるホテルを運営する人たち、我々が知っているブランドがついているとこですね。マリオットだとか帝国ホテルだとかニューオータニさんだとか。そういうところと、それから土地建物というものにある種投資をする人たち、所有する人たちというのが別の人たちになっています。そういうことが実は世界のもうほぼスタンダードになっているのです。
そういうところからすると、そういう流れにきちんと太刀打ちをして運営、経営ができるようなホテル業界あるいは観光業界の人が十分に育っているかというと、ちょっとこれが怪しくて、先ほどの僕のプレゼンテーションではないですが、ややもすると、どうも外国の方にかなりの利益が持っていかれる可能性が僕はあるというふうに、残念ながら心配している部分があります。特に金融のところで投資をされる方々のスペシャリストが大変そろっておられます。各委員は日経新聞を御覧になっているかと思いますが、ちょうど今、私の履歴書を書いているKKRというような会社は、まさにそういう会社です。ああいうところに優秀な日本人の方がどれぐらいいるかというと、実はまだそれほどいない。ですので、実はそういう、あまり表面からは見えないかもしれませんが、そこの部分が圧倒的に実は遅れておりまして、ホテルの現場というんでしょうか、オペレーションの現場で働いてくれる方々ももちろん重要なのですが、ちょっと誤解を恐れずに言えば、もしかすると、運営の現場で働く人材不足の方に関しては、外国籍、外国人の方にもっと入っていただくというようなことが、すいません、少なくとも世界のホテル業を見回すと、むしろそちらはあるのかなと。
そこももちろん重要なのですが、特に日本人を対象とした人材育成、教育ということで言うならば、むしろ今申し上げた、それが経営レベルというんでしょうか、実際にそれが特にいろんな外国のお金も含めて、資金を集める、あるいは不動産としてどのように活用していくのかというところのプロフェッショナルな人材が実は必ずしも多くありませんので、そこのところを育成する、そこのところを養成するというところに、実は僕の感覚から言うと、早く手をつけていただいたほうがいいだろうなというふうに思っております。
申合せの時間がほぼ来たと思いますので、以上で終わります。先生、どうもありがとうございました。