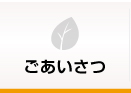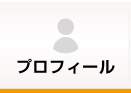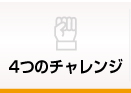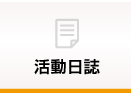第5期
2025年
2024年
第4期
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
第3期
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
第2期
2014年
2013年
2012年
2011年
第1期
2010年
2009年
2008年
2007年
府民文化常任委員会 参考人招致
質問事項
2024年11月1日
●オーバーツーリズム
ありがとうございます。公明党府議団の加治木と申します。阿部参考人、今日はありがとうございます。
先生が連載されました日経新聞の「オーバーツーリズムを超えて」、あれを私ともう一人、前に座っております大竹と、この先生の連載をまとめてコピーを取って読ませていただきました。今日はその最終回の分を上げていただいております。
改めて、ちょっと質問の観点ががらっと変わるんですが、オーバーツーリズムの根っこには、旅の恥はかき捨てという、日本人はそう言いますけど、そういうのがやっぱりどこかにあるんかなというのを非常に感じておりまして、先生のこの記事の中で、敬意を持った振る舞いが観光地のおもてなしの精神をさらに育むことになりますということも書かれています。恐らく先生はツーリストシップという言葉を聞かれたことがあると思いますが、この考え方とか、今度ここの委員会にも参考人で田中千恵子さんに来ていただくんですけど、この動き、今、先生から御覧になって、どないなふうにお考えか、ちょっとお聞かせいただけますか。
今のは、ツーリストシップに関してということでよろしいでしょうか。
旅の恥はかき捨て、そういう考え方は日本は結構あると思いますし、世界的に見ても、基本は結構あります、似たようなところが。これは、そもそも観光は余暇活動として行うというところに起因すると思いますが、非日常性を味わって、リフレッシュして日常生活をさらに質を高めていくというために観光が必要だと、これは国も言っていることですけれども。その際に、どうしても非日常性が刹那的な欲望といいますか、そっち方向と結びつきやすいというところがそもそもあったりとか、やっぱり気が大きくなっている、リラックスしているというときに、地元ではそう振る舞っていないことをやってしまうというのは、これは一般的に国を問わずあろうかと思います。
なので、そのツーリストシップみたいな考え方は極めて重要になってくると思いますが、これは結構、何でしょうね、世界レベルでそういうふうな啓蒙を、啓蒙という言い方じゃないかもしれませんが、啓発をやっぱりやっていかないと、なかなかぴんとこないところがあろうかなというふうに思います。というのも、リスペクトの出し方、よい振る舞いをと思っても、それ自体が国々によってまた異なってきますので、当然ながら共通事項はありますけれども、何か統一的に示せるものでもないかなというところがあるんですが。
コロナ禍の前後の議論で一つキーワードで出てきているのが、レスポンシブルツーリズムという言葉があって、責任ある観光なんですけれども、責任というのは、誰の何にかかっているかという話があります。レスポンシブル、これはいろんなアクターがレスポンシブルにならないと駄目だという話なんですが、当然ながら、観光客は地域の生活に敬意を払わなければならない。これはどういう意味かというと、やっぱり迷惑をかけないというところもあるかもしれませんし、それは振る舞いの問題なんですけれども、やはり旅のスタイルとして、恥のかき捨てにならない第一歩は、学んでから行くということだと思うんです。地域学習、そこがどういう地域で、どういう歴史をたどってであるとか、要するに学習の側面を今後は入れていかざるを得ない。学習というとなかなか堅くて、そんなことして旅行に行きたくないよというふうになるわけですけれども、そこはそんな完璧に、何か論文を書くわけではありませんから。地域側もそういうふうに理解をしてもらいたいというか、それを理解すると、うちに来てもらったときにもっと楽しめますよというような話をどういうふうに編集して、情報として出していくのか、周知していくのか。これが観光地側は結構重要になってくるんじゃないかというふうに思います。それを観光客のほうがうまく理解をできるのであれば、ツーリストシップと言わずとも、もう少し内在的にリスペクトというか敬意を持ち得ると思うんです。
そうすると、観光のマーケティングの問題ともなってくるんですけれども、どうしても観光のマーケティングが、それこそ食事であったりショッピングということになっていて、当然これは我々が旅行するときも極めて重要な楽しみではあるわけですけれども、その2点をアピールしていくときに、地域のよさとかを伝える余地があまりないといいますか。食事に関しては、もちろん食事にまつわる歴史を伝えることができると思うんですけれども、何かもう少し、どういう地域か、どういうところにこだわって見てもらえるともっと面白くなるというような情報が事前に共有される場がまだないというふうに思っていまして、そういうのを併せて検討していくことが、緩やかなツーリストシップの醸成につながっていくのではないかと考えます。
ありがとうございます。
またちょっとがらっと観点が変わりますが、何年か前に京都の府議会議員とお話ししていて、海の京都というのもやっていると。大阪人にしてみても、京都市内は新快速で30分で行けるぐらい近いところなんですが、舞鶴とか日本海側というのは、正直なかなか気づいていない。いわゆる京都の多様性を示す場所として非常にいい取組やと思うんですが、先生、この点に関しては何か御意見をお持ちでしょうか。
御指摘のとおり、観光の広域化の話を申し上げましたけれども、京都府のその取組は、とてもいろんな示唆があろうかと思います。
というのは、海の京都といったときに、京都府が日本海側の海に面しているというのは当然常識として持っているわけですが、改めて言われると、そうだ、海あったなとなるわけですね。その際に、あれは舞鶴だけじゃなくて伊根町なんかもそこに入っていますが、もう少し広域連携を促すような発想にもなっています。京都府の場合、そこは海の京都はDMOとしてやっていたりしますが、こういう一つパッケージングというか、キーワードで束ねていくという方法としても面白いなというふうには思っておりまして、海の京都シリーズだけじゃなくて、いろいろやっていますね。お茶の京都とか、森の京都だったかな、幾つかパターンを京都府はつくっているんですけれども。
そうすると、そういうまとまりとして確かにあるなというのが観光客のほうにも分かりますし、それがあるだけで候補に入ると思うんですね。行くかどうかはさておき。海の京都と言われると、ちょっと足を伸ばすには……、でも、1時間半で行けるかみたいなとこも含めて。だから、それは情報の出し方というか、情報の出し方の意味の持たせ方にすごく面白さがあるなと思って見てはいます。
なので、大阪も府で観光のことを考えるときには、少し広域性を持ったような視点での議論というのができると、より伝わるかなと思いますね。多分東京から来る場合、京都、大阪と行って、次に広島へ行くパターンというのが多いみたいですけれども、何かもったいないですよねというのが、多分府の立場からすると絶対あると思いますので。あるいは関空に来たときに、いきなりもう市に、真ん中に行くのではなくて、ちょっと違うとこも行ってみるみたいなのも含めてかもしれませんが、そういう広域化の一つの例として、京都府の例は極めて示唆に富んでいるとは思います。
あと、私はたまさか、今、関西広域連合の議員もやっておりまして、この間、この観光というのもテーマに取り上げたんですけど、ちょっと大阪府だけじゃないんですが、関西広域となったら、まさに京都も大阪も神戸も奈良も和歌山もと、もっといろんな可能性があるんやないかと思います。ここは先生はどのようにお考えでしょうか。
もちろん、そのレベルでも考えていけることというのはたくさんあると思います。広域で考えるときというのは、もう既にメインで定評のある観光地だけではなくて、その地域としてそこに来てもらうことが地域の発展につながると。行っていないところというのはもちろんたくさんあるわけなので、そういう戦略の中で、観光という経済活動を、今人気のあるところからどううまくトリクルダウンじゃないですけど、広げていくかという観点では、広域連合はとても重要だと思います。
先ほど京都府の話を申し上げましたけれども、それはあくまで都道府県でいうところの枠なので、実際もっと広域にわたるわけですよね。昔から三都物語とかいうように、広域にわたっていて、かつ、関西の場合は主要都市間がすごく距離が短い。それこそ30分単位でいろいろ移動できるというところがありますから、そこからさらにいろんなところへ行ってもらうであるとか。
広域連合でもう一つ考えられるのは、宿泊の問題を少し私は課題だとして今日は時間を費やしましたけれども、宿泊も、いろんなところに宿泊の可能性をもっと持たすような戦略とか計画というのは、より広域の行政組織じゃないと、なかなか発想として出てこないと思うので、そういうことができるといいんじゃないかなとは思うんですね。京都市に宿泊施設が集中し過ぎていますけれども、近隣の自治体にはあんまりないんです。例えば大津市とかは電車で10分ですけれども、ほとんどなかったりとか、亀岡にもあまりないですし、高槻にもあまりないですしということで、本来、その辺は、交通の便のよさも含めたときに、面白い宿泊施設がそういったところに増えてくると、多分泊まる先としての選択肢としてそういうところが浮上してくる可能性もあると思いますから、何か広域連合でできることというのは、私は観光に関して結構まだあるというふうには認識をしております。
先生、どうもありがとうございました。私からは以上です。