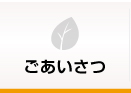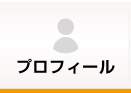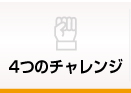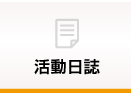第5期
2025年
2024年
第4期
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
第3期
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
第2期
2014年
2013年
2012年
2011年
第1期
2010年
2009年
2008年
2007年
本会議一般質問
質問事項
- ●大学生等若者への食費支援事業
- ●日本語指導が必要な児童生徒への支援
- ●英語教育推進事業
- ●情報活用能力の育成
- ●国際金融都市における高度金融人材の育成
- ●(仮称)大阪依存症センターの第三期ギャンブル等依存症対策推進計画への反映
- ●新大阪駅エリアのまちづくり
- ●淀川舟運の活性化に向けた流域のにぎわいづくり
※質問当日、映像機器のトラブルがありました。一般質問の内容に直接かかわらない部分は当方の判断で削除しております。
2025年6月12日
●大学生等若者への食費支援事業
公明党大阪府議会議員団の加治木一彦です。一般質問の機会をいただきましたので、通告に基づき、順次質問を進めていきます。
最初に、大学生等若者への食費支援事業についてお伺いします。
今(2025)年4月の消費者物価指数の総合指数は111.5と、前の年の同じ月に比べ3.6%の上昇に対し、食料に注目しますと、124.0と前の年の同じ月に比べ6.5%上がっていました。生活必需品である食料の高騰で府民生活は厳しい状況にあり、効果的な物価対策が求められています。
政府は、5月27日、米国関税措置を受けた緊急対応パッケージの一環として予備費の使用を閣議決定しました。大阪府も重点支援地方交付金の追加配分として約29億円が交付されます。物価高騰対策として、今次定例会にLPガス利用者支援と大学生等若者への食費支援が補正予算案として上程されました。大学生等若者への食費支援事業は、物価高騰の影響を強く受ける若者にお米クーポンや食料品を給付するものです。なぜ19歳から22歳を対象にしたのか、事業実施の経緯とその目的を伺います。
また、事業実施に当たり、以下の3点を求めます。1点目は、事業の早期実施です。秋頃の実施を想定しているようですが、物価高騰対策であることを考えれば、できるだけ早期に実施すべきです。2点目は、申請手続の簡素化です。第1弾から第3弾までの子ども食費支援事業の申請情報を活用するなど工夫すべきです。3点目は、使用期間の十分な確保です。進学や就職などで大阪にやってきて独り暮らしをしている若者もいます。世帯として考えた場合、1食当たりの食べる量が子ども食費支援事業の対象世帯より少ないでしょうから、長めに設定すべきです。
以上の3点も併せて、福祉部長にお伺いします。
本事業は、国からの重点支援地方交付金の配分を受けまして、新たな物価高騰対策として、子育て世帯に準じて強く影響を受ける大学生等若者を支援することを目的としております。物価高騰が続く中、本事業を効果的に実施するためには、お示しのとおり、事業の早期実施、申請手続の簡素化、使用期間の十分な確保の三点は重要と認識しております。
一つ目の早期実施につきましては、契約後の手続を迅速に進めて、できるだけ早期に事業実施できるよう取り組みますとともに、二つ目、申請者の負担軽減を図れるよう、子育て世帯対象事業で行っております簡易申請の活用も検討してまいります。三つ目、お米クーポン等の使用期間につきましても、これまでの実績を踏まえまして、安心して選択いただける期間を検討してまいります。
こうしたことを通じまして、大学生等若者の皆さんに一日でも早く、かつ確実に食料をお届けできるよう、しっかりと取り組んでまいります。
子ども食費支援事業と大学生等若者への食費支援事業では、対象者が違います。食料品の選択肢に若者向けのものを追加してください。
広報周知に当たっては、大阪や近隣府県の大学、専門学校など、当該年代の若者が集まる場所へのポスター掲示を依頼するなど、一人でも多くの対象者に情報が届くよう工夫をお願いしておきます。
2025年6月12日
●日本語指導が必要な児童生徒への支援
次に、日本語指導が必要な児童生徒への支援についてお伺いします。
スクリーンを御覧ください。
府内の公立小中高校に在籍する当該児童生徒は、令和6(2024)年5月1日現在、5599人と、令和2(2020)年に比べ約6割、2053人増えました。今(2025)年5月時点はさらに増えていることが見込まれます。児童生徒が使う母語数が増え、府内各地の小中高校への少数散在化も進んでいるとお聞きしています。(スライド1)
我が会派は、これまで日本語指導について、これまでの議会でも質問を重ね、全ての児童生徒が安心して学べる教育環境の整備を求めてきました。今(2025)年3月に公表した府立高校改革グランドデザインには、日本語指導に係る支援を充実させるため、大阪わかば高校を拠点として整備することがうたわれています。
大阪わかば高校は、外国につながる生徒が数多く在籍しており、大学や地域と連携しながら教育環境の整備に努め、生徒支援に力を入れている学校です。日本語指導が必要な生徒支援の中心的な役割を担う拠点校とするには、ハード・ソフトの両面から、さらなる学校の運営体制の強化が必要だと考えます。
この4月、文部科学省より、新たに「ことばの発達と習得のものさし」等が示されました。義務教育段階から高等学校段階までの外国人児童生徒等の言葉の力を適切に把握し、児童生徒一人一人に応じた指導目標や指導内容を決めることができる評価ツールです。大阪わかば高校をはじめ府内の小中学校も、作成に関わっているとお聞きしました。
私は、このものさしを各校が活用し、一人一人の言葉の力を踏まえた適切な指導や支援を進めていくことが重要だと考えます。
日本語指導が必要な生徒を支援するため、大阪わかば高校を拠点校とすることへの整備状況はいかがでしょうか。また、府内の学校で、ことばの発達と習得のものさしをどのように活用していくのでしょうか、教育長にお伺いします。
スライド1
日本語指導の拠点校となる大阪わかば高校において、これまで蓄積してきたノウハウに加え、体系的な日本語指導方法の確立とその教材開発をはじめ、オンライン講習や少数散在校への支援等、センター的機能を発揮するために具体的な検討を進めているところです。
また、ことばの発達と習得のものさしは、それぞれの児童生徒の現状を捉えて、支援の充実につなげることを目指すものであり、拠点校となる大阪わかば高校での活用はもとより、必要な全ての小中高等学校に配布した上で、より効果的な活用に向けた教職員研修を複数回にわたって実施するなど、指導力の向上を図ってまいります。
教育庁といたしましては、大阪で学ぶ全ての子どもが自らのルーツのある国、地域の言語や文化に誇りを持ちながら、将来、社会を支え牽引する希望であると捉え、誰もが安心して学べる教育環境の充実に努めてまいります。
2025年6月12日
●英語教育推進事業
次に、英語教育推進事業についてお伺いします。
府教育庁が、令和5(2023)年度から実施している生きた英語プロジェクトにより、ネイティブ講師の配置拡充、デジタル学習ツールの活用、児童生徒を対象とした研修の実施等、英語力向上に向けた取組が進んでいます。中でも、府教育庁が令和5年度にパッケージ開発した英語学習ツール、BASE in OSAKAは、1人1台端末を活用し、児童生徒にとっては英語力の向上、教員にとってはテストの採点などで負担軽減が見込めることから特に注目しています。
昨(2024)年度の府教育庁の調査研究によれば、BASE in OSAKAの利用頻度が高い児童生徒ほど英語力が向上していたとの結果が出ています。BASE in OSAKAは、英語での発話等に対し、即時にAIがフィードバックや評価を出すことができます。使えば使うほど児童生徒が自ら課題に気づき、改善しようとできたため英語力の向上につながったと考えられます。児童生徒の英語力をさらに高めるため、このツールを積極的に活用すべきです。
府教育庁は、BASE in OSAKAを活用し、どのような取組を進めていくのでしょうか、教育長にお伺いします。
英語学習ツール、BASE in OSAKAについては、昨(2024)年度の調査等を踏まえまして、今(2025)年度から全ての府立高校1年生に導入しまして、生徒の英語を話す力の育成に努めているところです。今年度は、国の事業を活用してBASE in OSAKAに新たな機能を追加し、英語を書く力を向上させる取組を行うこととしており、府内の公立小中学校及び高等学校十校を研究校に指定し、AIを効果的に活用した個別最適な学びについて調査研究を実施いたします。
今後、研究校における好事例の収集や研究成果の周知等を行うことにより、BASE in OSAKAのさらなる活用促進を図り、児童生徒の英語力の向上に向けた取組を推進してまいります。
2025年6月12日
●情報活用能力の育成
次に、情報活用能力の育成についてお伺いします。
現代の子どもたちは、スマートフォンやSNS等を通じ、日々膨大な情報に触れています。中には偏った情報や誤った情報も含まれているため、フィルターバブル等の問題が指摘されています。誰でも簡単に情報を発信できインフルエンサーになり得る流れがとどまることはないでしょう。単に情報を受け取るだけではなく、情報の真偽を見極め、複数の視点から考察する力や情報の背景、意図を読み解く力、メディアリテラシーを含めた情報活用能力がますます重要になってくると考えます。
府教育庁は、令和6(2024)年3月、情報活用能力について、義務教育9年間で発達段階に応じて体系的に育むことができるよう、独自に大阪府情報活用能力ステップシートを作成しました。府内全小中学校に配布し、府ウェブサイトにも掲載してあります。
学校現場は、子どもたちに情報活用能力を育むため、どのような授業をしているのでしょうか。また、府は情報社会を生きる子どもたちへの指導を今後どのように充実させていくのでしょうか、教育長にお伺いします。
情報活用能力は、子どもたちがこれからの情報社会を生きる上で欠かせない能力であり、現行の学習指導要領においても、学習の基盤となる資質能力として位置づけられています。府内の小中学校では、ステップシートに記載されている内容を参考に、様々な教科等で情報活用能力の育成を図っております。
例えば、子どもたちが目的に応じて複数の表やグラフを用いて情報を整理し発表する学習や、インターネットの情報と図書資料とを比較し、信憑性を確かめる学習を行っております。これらの事例については、府ウェブサイト等で広く公開をしているところです。
また、今年度から学校の特色を生かし、多様な情報手段を用いながら情報活用能力を育むことを狙いといたしまして、府域の小中学校16校をモデル校に指定いたしました。
今後は、市町村教育委員会と連携いたしまして、モデル校を中心に好事例を創出し、府域に広く普及、発信することで、各校の取組が充実するよう取り組んでまいります。
2025年6月12日
●国際金融都市における高度金融人材の育成
次に、国際金融都市における高度金融人材の育成についてお伺いします。
2022年3月にまとめた国際金融都市OSAKA戦略は、今(2025)年度末までに金融系外国企業等を30社誘致することを目標に掲げました。現在の進捗率は8割程度とお聞きしております。残された時間は少なくなってきました。目標達成に向け、一層の努力をお願いしておきます。
次の段階として、金融系外国企業等が大阪のまちに深く根を下ろし、地元企業との協業などでビジネスを持続的に発展させ、大阪、関西の経済成長に貢献してもらうことが大切です。必要な要素の一つが、大阪での活動を支えてくれる人材だと考えています。
3月13日、大阪府市の共催で、大学、企業の連携による大阪、関西での高度人材の育成をテーマにしたフォーラムがあり、私も参加しました。大阪、関西の金融機関や大学関係者ら約100社、130人が集まったそうです。参加者からは、企業が求めるテクノロジー人材の確保が難しくなってきているなどの意見が出ていました。
AIやブロックチェーンなどIT技術の進展などを見据え、複雑化する金融業務に対応できる高度金融人材を大阪で育成、金融系外国企業等に輩出できる仕組みづくりは、国際金融都市の実現に向け重要と考えます。
高度金融人材の育成に向けたこれまでの取組と今後の方向性を政策企画部長にお伺いします。
高度金融人材につきましては、国際金融都市の基盤の一つであり、ターゲット企業の大阪への呼び込みにも寄与するものと考えております。
また、金融系外国企業等と対話する中で、進出先となる現地で人材を確保したいとの声もお聞きしており、大阪でのビジネス成長を促す環境整備として重要と認識しております。人材育成の取組といたしましては、これまでに国際金融都市OSAKA推進委員会委員の大阪公立大学が、2022年度から金融分野のテクノロジー講座を実施しています。
また、国際金融都市実現に関する事業連携協定を締結している関西大学が、4月にビジネスデータサイエンス学部を開設し、金融業界で実践力のあるテクノロジー人材の育成に向けた取組を始めたところでございます。引き続き、在阪の大学などと連携しながら、金融系外国企業等のニーズも踏まえた高度金融人材育成の取組を強化し、ターゲット企業の大阪への進出の加速やビジネスの拡大につなげてまいります。
2025年6月12日
●(仮称)大阪依存症センターの第3期ギャンブル等依存症対策推進計画への反映
次に、(仮称)大阪依存症センターの第3期ギャンブル等依存症対策推進計画への反映についてお伺いします。
5月は、大阪府ギャンブル等依存症問題啓発月間でした。24日は、大阪府市、堺市が主催で、中之島公会堂で「知ろう!気づこう!依存症」と題したイベントがあり、私もその場におりました。人気声優が出演したり、ラジオ番組の公開収録も兼ねていたりしたことで、ギャンブル等依存症に興味関心の薄かった人たちも来てくれていたのではと感じました。
翌25日は、全国ギャンブル依存症家族の会大阪と公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の主催で「広がるオンラインカジノ 迫る大阪IR 進めよう依存症対策」と題した特別セミナーがありました。パネリストとして登壇された府議の皆様、大変にお疲れさまでした。こちらのセミナーは、ギャンブル等依存症で悩まれている方の御家族が多く参加していました。府に対し、依存症対策にもっと力を入れてほしいとの切実な願いが痛いほどに伝わってきました。
府は、依存症対策の拠点として、相談、医療、回復のワンストップ支援機能を持った、(仮称)大阪依存症センターの設置に向け検討を進めています。今(2025)年度は、令和8(2026)年度から10(2028)年度までを期間とする第3期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画をまとめる時期に当たります。これまでの取組の充実にとどまらず、同センターの機能や開設時期など、具体的な内容を次期計画に位置づけることが必要と考えます。健康医療部長の所見をお伺いします。
府内におけるギャンブル等依存症に関する相談件数は増加傾向にありまして、近年のオンラインギャンブルの普及等により、相談内容も多様化してきていることから、今後、相談、医療、回復といったワンストップの支援は、さらに重要性が増すものと認識をしております。
このため、現行のギャンブル等依存症対策推進計画におきましては、これらのワンストップ支援や普及啓発等の強化を基本方針に位置づけているところであります。この間、依存症への理解促進のため、シンポジウムの開催やポータルサイトを通じた情報発信の充実強化に取り組むとともに、関係機関とのネットワーク構築による切れ目のない支援体制づくりを進めてきたところであり、次期計画におきましても、引き続き重点的な柱に位置づけ、取り組むこととしております。
お示しの(仮称)大阪依存症センターにつきましては、昨(2024)年度、センターが担う4つの機能のうち、相談から回復までのワンストップ支援と普及啓発、情報発信の機能につきまして検討会議での議論を踏まえ、取りまとめを行ったところでございます。
引き続き、残された調査分析や人材養成の2つの機能につきまして検討を進め、次期計画に具体的に位置づけるとともに、IR開業までに開設できるよう、着実に準備を進めてまいります。
同センターの相談、医療、回復のワンストップ支援、普及啓発、情報発信の機能は既に昨(2024)年度取りまとめたとのことです。拠点や人員の確保が一朝一夕でできないことは十分に承知しておりますが、ギャンブル等依存症対策は現在進行形の課題です。一日も早い同センターの設置を要望しておきます。
2025年6月12日
●新大阪駅エリアのまちづくり
次に、新大阪駅エリアのまちづくりについてお伺いします。
リニア中央新幹線や北陸新幹線の全線開業に向けた動きなどを見据え、民間の活力を引き出していくことが新大阪駅エリアのまちづくりに必要です。現在、まちづくり方針に沿って関係者が連携し、民間都市開発の具体化に向けて取り組まれていることと認識しております。
昨(2024)年6月の一般質問でも、民間主体のまちづくりに向けた機運醸成を取り上げました。キャッチフレーズの作成や戦略的なプロモーションを通じて、さらなる機運醸成に努めるとの趣旨の答弁がありました。
スクリーン、お願いします。
「新しいの、その先へ 新大阪」が、本(2025)年1月30日に開かれたまちづくりシンポジウムでキャッチフレーズの最優秀作品に選ばれました。先日、梅田の地下街のデジタルサイネージで、これが実際に流れているところを見ました。私も非常に気に入っております。(スライド2)
関係者が協力してまちづくりを進める上での共通の指針となるまちづくり方針は、6月末に更新版が公表されるとお聞きしております。3月の新大阪駅周辺地域まちづくり検討部会で、新たに十三駅や淡路駅周辺のエリア計画を盛り込むことを受けたものです。新しいまちづくり方針の下、機運醸成に向けたプロモーションを継続して進めていくことが重要と考えます。現状と今後の取組を大阪都市計画局長にお伺いします。
スライド2
新大阪駅エリアにつきましては、民間都市開発の機運を高めていきますためにも、新大阪駅周辺地域まちづくり方針に基づきまして、関係者と連携を取りながら効果的なプロモーションに取り組むことが重要であると認識しております。このため、新大阪駅周辺地域プロモーション検討会を設置いたしまして、昨年度は鉄道利用者、地元の方々、さらには若い世代などをターゲットとした広報活動や、シンポジウムにおけるキャッチフレーズの決定など、様々な手法によるプロモーションを実施してきたところでございます。
今(2025)年度は、8月に万博会場で開催する大阪ウイークにおきまして、グランドデザインの取組と併せまして、新大阪駅周辺地域のまちづくりを広く情報発信いたしますとともに、主要駅のデジタルサイネージにおきましても、お示しのキャッチフレーズ「新しいの、その先へ 新大阪」を活用いたしましたまちの将来イメージを掲示するなど、幅広くプロモーションを展開してまいります。引き続き、世界有数の広域交通ターミナルの実現に向けまして、関係者との連携の下、戦略的なプロモーションをはじめ、駅とまちが一体となった人中心のまちづくりを着実に進めてまいります。
2025年6月12日
●淀川舟運の活性化に向けた流域のにぎわいづくり
最後に、淀川舟運の活性化に向けた流域のにぎわいづくりについてお伺いします。
大阪・関西万博を契機に、淀川流域の活性化に向けた様々な取組が進んできました。
スクリーンを御覧ください。
本(2025)年3月16日、淀川大堰閘門及び十三船着場利用開始記念報告会がありました。こちらは、テープカットの様子です。(スライド3)
次、お願いします。
淀川大堰閘門、愛称「淀川ゲートウェイ」の完成で大阪湾から淀川本流を通り、枚方、京都方面へ船の往来が可能となりました。(スライド4)
もう一枚お願いします。
淀川ゲートウェイを航行する船から撮影したものです。十三船着場周辺は、国のかわまちづくり計画に基づき、民間事業者がバーベキュー広場などのにぎわいづくりを計画しています。(スライド5)
万博開幕後の5月10日、11日の淀川舟運フェスティバルで、淀川ゲートウェイと十三船着場を活用し、初めて京都方面から十三まで観光船が運航され、盛況だったそうです。
淀川流域は、十三だけでなく、枚方のかわまちづくりをはじめ、摂津市鳥飼や守口市佐太の船着場周辺などでも、様々なイベントが開かれてきました。
私は、昨(2024)年6月の一般質問でも、舟運活性化による淀川流域のにぎわいづくりの取組状況についてお聞きしました。それぞれの船着場を舟運でつなぎ、人々が行き交うことで流域全体ににぎわいを広げるなど、点から一本の線へ淀川流域の魅力を高めていくことが重要であり、万博を契機にさらに広がることを期待しています。
大阪・関西万博が開幕した今、改めて淀川舟運の活性化による流域のにぎわいづくりについて、その取組状況を大阪都市計画局長にお伺いします。
スライド3
スライド4
スライド5
淀川沿川におきましては、舟運を生かした魅力あるまちづくりの推進に向けまして、沿川自治体や民間団体等との連携により、かわまちづくりや地域資源を生かした取組を進め、にぎわいを創出することが重要と認識しております。
お示しの淀川舟運フェスティバルにつきましては、国を中心に本府も参画いたします淀川舟運活性化協議会において開催されたものであり、淀川大堰閘門を通過する観光船が運航され、募集40名の定員のところ250名を超える応募があったと聞いております。
さらに、同協議会では、万博開催期間中、十三船着場と夢洲を舟運で結ぶ社会実験を予定しておりまして、これに合わせて、本府が事務局を務めます淀川沿川まちづくりプラットフォームが中心となり、舟運と沿川地域のイベントを連携させ、各地の見どころをめぐる周遊ツアーを開催するなど、淀川沿川のにぎわいを流域全体へ広げる取組を進めてまいります。
引き続き、国や沿川自治体等と緊密に連携をいたしまして、淀川舟運の活性化による沿川のにぎわいづくりに向けて積極的に取り組んでまいります。
私の2問目の質問のときにスライドをお見せできずに大変失礼をいたしました。ぜひとも御覧いただきたかったのですが、非常に残念です。
以上をもちまして、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。