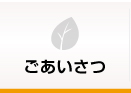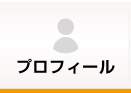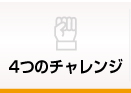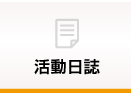第5期
2025年
2024年
第4期
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
第3期
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
第2期
2014年
2013年
2012年
2011年
第1期
2010年
2009年
2008年
2007年
府民文化常任委員会質疑
質問事項
2025年3月12日
●能登半島地域の子ども大阪観光招待事業
公明党府議団の加治木一彦です。本日結びの一番でございます。9個、質問項目がございます。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
まず1問目、能登半島地域の子ども大阪観光招待事業についてお伺いをいたします。
先日の我が会派の代表質問で、2月26日に始まりました本事業の招待者の募集につきまして、対象となる子どもたちや保護者の方々が募集を知らずに応募ができなかったということがないよう、適切な周知を行うことが必要であると府民文化部長へお伺いをしました。
4市町の教育委員会の協力を得ながら、学校経由のチラシの配布や、学校から保護者への連絡ツールを活用することで、各御家庭にしっかり届くよう周知を図っていると答弁をいただきました。
現在の募集は3月18日まででありますが、5月にも追加の募集をされるとお聞きをしております。そのときにはまた適切に御対応いただきたいと思いますので、今日は、その詳細についてあれこれお聞きをいたします。
本事業で対象となる子どもたちの人数、そしてまた、対象となる子どもたちや保護者の皆様への招待者募集につきましてどのように周知を図っているのか、府民文化部副理事、お願いいたします。
お答えします。
本事業の対象となります小学校5年生、6年生及び中学生の子どもたちの人数についてですが、募集を行うに当たりまして、対象地域の奥能登市町から聞き取りを行い、対象人数は約1200人と確認をしています。
また、周知の方法ですが、2月26日の募集開始に向けて、募集用のチラシを奥能登4市町の教育委員会を経由して各小中学校から対象の児童生徒に配布をしました。
加えて、各御家庭の保護者にきちんと見ていただけますよう、各小中学校にも御協力をいただいて、メールで学校から直接保護者へ連絡できるツールも活用させていただいて、各御家庭にしっかり届くよう周知を図っております。
また、5月の追加募集においても重ねて丁寧な周知を行いたいと考えております。
ありがとうございます。
5月の追加募集の際にも、対象となる各御家庭に周知が行き届きますようお願いいたします。
うちも、今現在、小学校4年生の息子がおりますが、忙しいと、持って帰ってきたプリントをちゃんと読んでなかったりするんですね。1日、2日ぐらいやったらいいとは思うんですが、ほんと、ゆったりと周知期間を取っていただいて、より多くの人に手を挙げていただく機会がありますようお願いいたします。
同じく先日の代表質問で、対象要件の見直しや費用負担の軽減などにつきまして、参加しやすい仕組みづくりに努めるということで御答弁をいただきました。こちらにも感謝を申し上げます。
次に、参加される子どもたちが大阪のファンになり、また大阪に来たいと思ってもらえるような旅行内容にすることが大事ではないかと考えます。今回の旅行の行程や内容等につきまして、また府民文化部副理事、お願いいたします。
今回、参加者が柔軟にスケジュールを調整して応募いただけますよう、7月25日から27日、8月2日から4日、8月8日から10日の3つの旅行日程を設定しています。
旅行の主な行程ですが、集合・解散場所は、奥能登4市町の中心部かつ駐車場が確保できますのと里山空港とし、のと里山空港からはバスで金沢駅まで移動となります。その後は、関連企業にも御協力をいただき、金沢-新大阪間は新幹線等での移動を予定しております。
大阪観光の主な内容ですが、大阪・関西万博では、シグネチャーパビリオン、大阪ヘルスケアパビリオンや水上ショーといったパビリオンやアトラクション、万博会場からアクセスのよいユニバーサル・スタジオ・ジャパン、その他、大阪市内観光といった内容を、現在、検討調整しているところでございます。
引き続き、万博と大阪の魅力を満喫し、多くの子どもたちに笑顔になってもらえますよう、旅行内容の詳細を検討してまいります。
来ていただいた子どもたち、また、その御家族が笑顔になって、あっ、よかったと思っていただける内容にしていただきますようお願いいたします。
本事業は寄附を募って実施するものです。2月時点で約6000万円、寄附が見込めるということで、募集人員は320人というふうに設定されたとお聞きしております。現時点の申込状況についてお聞かせください。
お答えします。
応募状況ですが、本日の3月12日9時現在で375件の応募があり、そのうち、子どもの申込人数は470人となっております。これは、保護者を含めますと845人となっておりまして、既に募集人数の320人を超えている状況です。
今後募集する人数についてですが、新たに120人程度追加し、合計440人を招待するという目標を立てて、5月に追加の募集を行う予定です。
引き続き、5月末まで、個人、企業の皆様の御寄附を頂けるようお願いしていくとともに、一人でも多くの子どもたちを招待できますよう、しっかりと取り組んでまいります。
よろしくお願いいたします。
既に845人と、320人を上回っておりますので、ほんと、一人でも多くのお子さん、御家族に来ていただきたいというような、その気持ちはこちらもやまやまでございます。
皆さんからより多く寄附を募っていただくことも大事やと思いますが、現実を考えますと、手を挙げても、やっぱり、こぼれ落ちてしまう御家族が出てくるんやないかなと危惧をしております。もし残念ながら今回縁がなかった皆様に対しても、ここは地元の市町と御協議いただきまして、何がしか大阪の気持ちが届くような工夫をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
2025年3月12日
●大阪都市魅力創造戦略
次のテーマに移ります。大阪都市魅力創造戦略についてです。
昨(2024)年10月の府民文化常任委員会で、現行の大阪都市魅力創造戦略2025の後継戦略についてお聞きをいたしました。
大阪府市都市魅力戦略推進会議という専門家会議での議論を始め、併せて、観光振興施策の企画立案等に必要なデータ収集や分析の調査を実施しているとのことでありました。
この次期戦略の策定に関する現在の進捗状況につきまして、企画・観光課長、お願いいたします。
大阪都市魅力創造戦略2025の後継となる次期戦略の策定に向けましては、委員からお示しございました大阪府市都市魅力戦略推進会議を、これまで、令和6(2024)年9月と12月の計2回行いまして、この3月末には3回目の会議を開催する予定としております。
会議の中では、万博終了後の大阪において都市魅力分野として重視すべき視点など、活発な議論が展開され、各委員から様々な御意見を頂戴しているところでございます。
また、観光振興施策の企画立案等に向けた調査につきましては、統計データ分析などのデスクリサーチや関係事業者へのヒアリングの結果などをまとめた報告書が間もなく完成する予定というふうになっております。
引き続き、この調査結果も踏まえながら、検討会議におきましてさらなる議論を深め、来年度の次期戦略策定に向けて、しっかりと取り組んでまいります。
次期戦略の策定に当たりまして、さきの委員会では、持続可能性、レジリエンスが大事な視点である、このように申し上げました。それに加えまして、大阪を訪れた人が大阪の魅力を満喫して満足して帰っていく、さらに、帰って、大阪はいいところだと、その魅力を大いに宣伝してくれる、そのためにやらなければならないことはいっぱいあると思います。
公益財団法人日本交通公社の機関誌「観光文化」の第264号に「世界の観光ダイナミズム2024」と題した特集記事がありました。その中に、「オーバーツーリズムと向き合う欧州都市の観光地マネジメント」ということで、オランダのアムステルダム市が取り上げられています。
2002年に「I amsterdam」とのキャッチコピーで観光客誘致に乗り出したアムステルダム市。2015年以降は、バランスの取れた都市として、住民中心、生活の質を第一に据えるように変化したとありました。
今後、次期戦略を策定するに当たりまして、こうした海外の先進的な事例や様々な立場の方々の意見も踏まえ、議論を進めていってもらいたいと考えます。企画・観光課長に御所見を伺います。
大阪の都市魅力向上に当たっては、持続可能な都市像として、多くの人が訪れることによるにぎわいの創出と、住民生活との調和という視点は重要な考え方の一つであるというふうに認識をしております。
次期戦略の議論に向けましては、住民生活への影響も考慮して、観光客の時間的、また空間的分散なども踏まえながら、新たな都市のにぎわいづくりについて、有識者からの専門的意見を伺いたいというふうに考えております。
今後とも、委員お示しのような海外の先進事例などを含めた幅広い視点を持って検討を行いまして、新しい時代にふさわしい大阪都市魅力創造戦略となるように議論を深めてまいります。
先ほどの「観光文化」、ここでアムステルダム市のことについてもうちょっと詳しく書いてありました。
2020年から、シティーセンターアプローチという考え方、方針の下に、市の中心部の課題を広範にまとめて取り扱うことにして、優先順位を設定して的を絞った対策を取るようになっています。
ここでも、やっぱり、言わばオーバーツーリズムの課題というのがアムステルダム市の中心部で生じているということで、そこに対策を向けていこうということだそうです。基本的な考え方として、「私たちはオープンで国際的な都市中心部として国内外からの訪問者を引き続き歓迎するが、それは彼らが私たちと同じ基本的価値観を支持している場合に限る」と宣言しています。
観光経済ビジョン2035、これではさらに踏み込んで、自分たちが望むことと取り除きたいこと、望む観光と望まない観光ということを明確に区別しております。
詳しいことは、この「観光文化」をお読みいただくとしまして、「客観的データを用いて状態を判定し、観光をより適切に促進していく視点が重要となろう」と、ここでも指摘されており、私も同感であります。これからつくっていかれるに当たりまして、様々御検討いただければと思います。
2025年3月12日
●大阪府内周遊ツアー検討事業
それでは、次のテーマに移ります。午前中の森田委員からもございました大阪府内周遊ツアー検討事業でございます。
府は、民間主導で府内周遊ツアーの展開、継続を目指した大阪府内周遊ツアー検討事業を実施するとのことです。万博で一層の来阪観光客が見込まれる中、初めて大阪に来た人、また、時間に制約がある人、そういう人たちにとっては、周遊観光バスのように気軽に周遊できる手段があれば、非常にありがたいと思います。分かりやすい話で言えば東京のはとバスです。あれ、行ったら、それこそ、ざあっといろんなところに、自分の興味関心に合わせて連れていってくれるわけです。
また、府内各地の魅力的な地域資源を巡り、地元の食なども楽しめる周遊ツアーを複数提供できれば、万博のときに限らず、次回以降、大阪来たときに今度はあのツアーに行こうかなどのきっかけになるのではないかと思います。
こうした周遊ツアーを検討するに当たりまして、利用者のニーズをしっかりと把握し、ターゲットを明確にする必要があります。また、次、大阪に来るときにも楽しんでいただくために、この周遊ツアーが継続して実施されることが何より不可欠であります。
本事業を実施することで、民間事業者ならではの発想と旅行者目線により周遊ツアーが造成され、また、将来的には民間事業者が主体となって事業が継続されることを期待しております。具体的な進め方につきまして魅力づくり推進課長にお伺いいたします。
大阪府内周遊ツアー検討事業では、バスやタクシーなどの交通事業者や旅行事業者等への委託を想定しておりまして、こうした民間のノウハウやネットワークを生かして、観光客のニーズに沿った複数の周遊ツアーを提案いただくこととしております。
また、モデル事業実施後の効果検証では、改善点等に加え、事業者に対する府の支援の在り方につきましても、外部有識者から御意見等をいただくこととしており、その内容を踏まえ、次年度以降の取組につなげていきたいと考えております。
こうした取組を通じて民間主導の周遊ツアーが展開され、来阪観光客に府内各地を楽しんでいただけるよう、仕組みづくりを進めてまいります。
国連世界観光機関とベトナム文化スポーツ観光省が、昨(2024)年12月、第1回地域発展のための観光に関する国際会議というものを開きました。この場で、ルーラルツーリズム--ルーラルというのは田舎とか田園という意味の形容詞ですが、現在の観光トレンドと一致しているとのまとめがなされています。
民間事業者主体で様々な周遊ツアーが継続的に展開されるために、有識者の意見を基に、それぞれの効果を検証することは非常に重要なことと考えます。
さらに、どの観光スポットがツアー参加者に好評だったのか、周遊ツアーを実際に運用するに当たって何が課題だったのかなど、現場の声につきましても、モデル事業実施時にアンケート調査や事業者からのヒアリング等で収集をし、翌年度以降の府の方針決定に生かしてください。
府域への周遊観光の可能性を探る今回の事業、私も期待しております。大阪を訪れた観光客に今まで知られていない魅力を発信できるようお願いいたします。
2025年3月12日
●万博のインパクトを生かしたMICE誘致
それじゃ、次の質問です。万博のインパクトを生かしたMICE誘致についてです。
アメリカのビジネスメディアであるフォーチュン・ビジネス・インサイトによれば、世界のMICE市場の規模は、2023年に9043億米ドルだったそうです。2024年から2032年までの間に、平均で年間成長率が約9%、これでいきますと、2032年の市場規模は1兆9327億米ドルと、2023年に比べて2倍以上増えると予測しております。
MICE関連産業が地域の経済成長にとって欠かせない重要な産業分野になっていくことを示しているのではないでしょうか。大阪も後れを取ることなく、MICE誘致に取り組んでいくべきと考えます。
間もなく、世界最大級のMICEとも言える大阪・関西万博が始まります。特に、大阪は健康医療分野に強みを有しており、いのち輝く未来社会の実現や健康寿命の延伸をテーマとして掲げる万博をきっかけに、この強みをアピールしてMICE都市としての認知度向上を目指すべきと考えます。世界的にMICE市場の著しい成長が進む中で、大阪でもMICE誘致を強化する必要があると考えます。
万博のインパクトを生かしたMICE誘致の取組につきまして企画・観光課長にお伺いいたします。
国内外から多くの人々が参加するMICEの開催は、会議施設や宿泊施設のみならず、交通や飲食をはじめ、開催を支えるあらゆる産業分野におきまして直接的な経済効果が見込まれるとともに、ビジネスイノベーションの機会創出のほか、都市格の向上、また、都市のブランド化にも大きく寄与するものでございます。
間もなく開幕します大阪・関西万博には、世界中から最先端の技術が集結するほか、研究者や技術者といった多くの人々が参加されるということから、大阪のMICE都市としての認知度を向上させる絶好の機会となります。
そのため、昨(2023)年度から、大阪市や大阪観光局と連携しまして、万博を契機としたOSAKA国際会議助成金によるMICEの開催支援を行うなど、万博と併せた重点的な誘致の取組を進めているところでございます。
また、万博終了後にはIRの開業も控えておりまして、そこには世界水準のオールインワンMICE拠点とも言われる国際会議施設などの整備が予定されているところです。
そのような大阪の優位性も最大限活用しながら、今後とも、関係機関と連携しまして、大阪の成長に不可欠なMICE誘致に取り組んでまいります。
MICEの誘致は、大型になればなるほど、準備時間、また、他都市との競争などなど、いろんな大変なことがあるかと想像いたします。
今回、万博を契機としたOSAKA国際会議助成金というのは令和7(2025)年度までとお聞きをしております。会議の主催者が助成金だけで選ぶことはないとは思いますが、あったほうがいいと思うのは、誰しも人情で思うことやと思います。場所を提供する大阪府として、何がしか、助成金の継続を要望しておきます。
2025年3月12日
●外国人観光客徴収金の検討状況
次に、外国人観光客徴収金の検討状況についてお伺いいたします。
日本政府観光局が公表した今(2025)年1月の訪日外国人旅行者数は378万1200人で、単月で過去最高を記録したとのことです。府庁との往復で地下鉄を利用している私にしてみれば、ほんとに、ターミナル駅--梅田とか新大阪とか、外国人旅行者でほんまにあふれかえっているというのを実感しております。
大阪府は、昨(2024)年3月、吉村知事が、外国人観光客に対して一定の負担を求める徴収金制度、いわゆる外国人観光客徴収金制度の創設を検討すると表明しました。翌4月、附属機関である大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議に検討を諮問されています。
この8月にその検討会議から第一次の答申が出されました。徴収金は、外国人観光客のみに負担を求める必要性や目的、使途など、制度の根幹から検討が必要であること、租税条約との関係や財源確保の手法など、整理すべき課題も多いという理由で、継続して審議することとお聞きしております。
外国人観光客徴収金に関する現在の検討状況につきまして、こちらも、企画・観光課長、お願いいたします。
外国人旅行者の増加に伴い発生する課題への対応及びその財源に関する検討につきましては、委員お示しのとおり、昨(2024)年4月から調査検討会議で議論が開始されまして、国内ではこれまでに導入された事例がないということや、整理すべき課題が多いということから、国外における事例も研究しながら、議論を継続するということになったところでございます。
直近では、昨(2024)年の12月にこの会議が開催されまして、国内における宿泊税以外の観光財源、国外における外国人を対象とした徴収金や二重価格の事例調査に関する中間報告なども参考にしながら、各委員の専門的見地から検討を進めていただいたところでございます。
この会議におきましては、国外事例を追加で調査して、その結果を踏まえながら、制度設計上の課題や法的位置づけなどをさらに深掘りした上で、制度の実現可能性について整理していく必要があるというふうな御意見がございましたので、引き続き、この検討会議で議論いただき、その答申も踏まえて、府としての対応を検討してまいりたいというふうに考えています。
先日、国は、一人1000円を徴収している国際観光税、いわゆる出国税を引き上げる方向で検討するとの報道がありました。訪日外国人観光客の急増に伴うオーバーツーリズム対策などの財源にも充てる方針とのことです。
大阪府は、既に観光財源としての宿泊税を徴収し、その引上げも決まっています。オーバーツーリズムの未然防止にも充てるとのことで、新たに財源を求める必要があるのか、疑問を感じております。
日本政策投資銀行と日本交通公社が訪日外国人旅行者を対象に調査を実施し、2024年の10月11日に結果を公表しております。観光資源、施設の混雑緩和や保護のため金銭を負担することに対し、賛成、やや賛成を合計すると63%となり、2019年調査に比べて20ポイント上昇しています。徴収される側の抵抗感も薄れているのかもしれません。
ですが、新たな徴収金制度をつくるとなれば、なぜ新たな負担金を求めるのかといったそもそもの徴収目的や、他の財源とのすみ分けを明確にするのは当然と考えます。整理すべき課題は山積しております。調査検討会議でしっかりと議論いただき、その御判断をされるよう求めておきます。
2025年3月12日
●万博会場での子どもたちの参加機会
続きまして、万博会場での子どもたちの参加機会についてお聞きをいたします。
いよいよ来月、万博が開幕いたします。未来社会の実験場をコンセプトとする今回の万博で、次世代を担う子どもたちが最先端の技術やサービスに触れるだけでなく、例えば、子どもたち自らの考えを発表したり、ダンスや音楽などを披露できれば、将来にわたる大きな刺激、財産になると考えます。
この件につきましては、令和3(2021)年9月定例会の我が会派の代表質問で、子どもたちのすばらしいアイデアを万博会場で発表する機会を提供してはどうかと提案をし、大阪パビリオンで検討する旨、当時の政策企画部長から答弁をいただいております。
万博の会期中、大阪ヘルスケアパビリオンをはじめ、万博会場で、子どもたちが自らの考えやパフォーマンスを発表、披露できるイベントの開催など、子どもたちの参加の機会はどれくらいあるのでしょうか、参加促進課長、お願いいたします。
万博会場における子どもたちの参加につきましては、国の万博アクションプランにおきましても位置づけられておりまして、例えば、経済産業省では、デジタル学園祭として、7月19日から21日、全国の中高生等が参加いたしまして、テクノロジーを活用して社会課題を解決するコンテストの実施が予定されているところでございます。
大阪府市におきましても、府内市町村と共に開催いたします大阪ウイークでは、7月の27日から29日に、多くの小中学生や高校生等に出演していただき、吹奏楽やバレエ、歌劇、ダンスやバトントワリングなど、子どもたちの熱気あふれるパフォーマンスを披露するステージを行うこととしております。
また、7月30日には、高校生が、健康や多様性など万博のテーマに関連するトピックにつきまして自らのアイデアを発表する、仮称ではございますが、高校生EXPOサミット2025を開催することとしております。
そのほか、府の教育庁や市町村などの主催イベントにおきましても、和太鼓や書道等の実演やアート作品展示など、子どもたちが参加できるプログラムを多数実施する予定としております。
これらに加えまして、大阪ヘルスケアパビリオンでは、協賛企業等が様々な企画を準備しているところでございます。例えば、8月の17、18日には、いのちをテーマにした高校生による音楽の演奏、お笑いや日本舞踊、スピーチなど多様なステージを展開することとしております。
引き続き、市町村や関係団体等と連携しながら、多くの子どもたちが万博に参加することで、それぞれが未来社会を考える契機とし、将来に向けて主体的に行動していくことにつながるよう、しっかり取り組んでまいります。
ありがとうございます。
やはり、発表の場があるというのは非常に子どもにとっても励みになると思います。それが、まして万博という舞台であればなおさらすばらしいと感じます。ぜひともいいものになりますようにしっかりと御支援のほど、お願いいたします。
2025年3月12日
●万博開催に向けた機運醸成
続きまして、開幕まであと一か月となりました機運醸成についてお聞きをいたします。
これまでも、我が会派は、様々、機運醸成について議会で質問したり、また、課題解決に向けて府への要望を提出をしたりしてまいりました。直近では、2月4日、入場券の購入手続の改善や販売促進に向けた広報宣伝を充実させることなどを府に申し入れました。
開催が近づいてきたからでしょうか、パビリオンの展示内容等、万博にまつわる情報が続々と報道されております。今朝も、私の母校の先輩が外国パビリオンの設計に当たったという新聞記事が出ておりまして、おっと朝から驚いた次第です。やっぱり、自分の知っている人がこういうところに出ていると、万博をより身近に感じるというのがあるかと思います。
また、4月5日と6日に実施するテストランには、定員の九倍近い応募があったということで、これも、やはり、万博への関心の高さの表われやないかと感じております。
前売り入場券は、ようやくと発売枚数が800万枚を超えたとのことです。2005年の愛・地球博--愛知万博のときは、934万5000枚、前売り券が売れまして、そのうち、約130万枚が開幕直前の1か月だけで売れた。誰がどこで買うたんか分からへんのですが、直前の1か月でこれだけ売れたという実績、過去があります。ラストスパートの機運醸成というのは非常に重要なものだと考えます。
万博の魅力や具体的な内容などの情報発信に加え、テストランなど様々な機会も活用して、開幕に向けてのラストスパートの情報発信が必要だと考えます。地域連携担当課長、お願いいたします。
万博の具体的な中身の発信につきましては、博覧会協会と連携して、ウェブサイトやSNS、広報誌、さらには雑誌との連携などにより、情報発信を進めてまいりました。
これらに加えまして、開幕直前期の重点的な取組といたしまして、協会におきましては、新たにインフルエンサーを活用したテレビCMを今(3)月7日から全国で放映を始めているほか、19日には公式ガイドブックの発売が予定されているところでございます。
府市におきましても、旅行雑誌や府政だより3月号の万博特集に加えまして、明日、13日から、ショート動画を活用したウェブ広告の集中的な配信等に取り組んでまいります。
さらに、来(4)月5日、6日のテストランの来場予定者に対しまして、実際にパビリオン等を体験した感想につきましてSNS等を通じて発信いただけるよう働きかけてまいります。
引き続き、協会等とも連携し、より多くの方々に万博に行ってみたいと思っていただけるよう、様々な機会を活用した機運醸成の取組を進めてまいります。
12年前に府民文化常任委員会に所属したときに、いわゆる情報発信とか広報宣伝ということで、広告業界の人やったら、それこそ古典的な法則であるアイドマの法則を使うという話をしたんです。アテンション--注意を引く、インタレスト--興味を持ってもらう、デザイアー--それを欲しいと思う、メモリー--その商品名を記憶して、アクション--実際買いに行く。
その時点、12年前で電通さんの方が言っていたんですが、AとIは一緒やと。その後、S--サーチ、検索する、アクション--買いに行く、その結果をシェアするということだったんですが、さらにもう一歩進んでいまして、サーチの後にC--コンペアが入るアイスカス(AISCAS)という考え方が提唱されています。
そうすると、まさにそうなんです。万博で、まさにテストランなんかで来てくれはった人たちがどういう情報を発信するかというのは非常に大事なことになると思います。Aさんは、これ面白いやんと言うてくれたけど、Bさんは、何かこれ違うとかね。
もちろん、それぞれの感じ方ですから、こうしろとかああしろとか、もちろん強制のしようはないんですが、明らかにこれはおかしいやろうという情報に対しては、こちらの主催者側から発信することも必要でしょうし、これはそのとおりやと盛り上げてもらうような、そういった工夫もうまく考えていただければと考えております。
2025年3月12日
●クレジットカード会社と連携したインバウンドの誘客事業
では、次のテーマに移ります。クレジットカード会社のVISAと連携したインバウンドの誘客事業についてお伺いをいたします。
大阪広域データ連携基盤--ORDENやmy door OSAKAを活用し、万博開催期間に、府内各地域の観光施設や店舗の情報を海外の旅行者に直接発信し、インバウンドの府内市町村への誘客を図るとのことです。本事業の目的と概要につきまして戦略企画課長にお伺いいたします。
本事業は、ORDENとmy door OSAKAを活用し、VISA社との連携の下、来阪するインバウンドに対して、府内市町村の観光PRメールの発信や飲食店クーポンの発行等を行いまして、広く府内への誘客を目指すものでございます。
関西国際空港を利用するインバウンドの方々が空港と万博会場を往復するだけではなく、行き帰りの際に周辺地域を周遊することを狙いといたしまして、泉州地域の施設や店舗を対象に事業への参加を呼びかけているところでございます。
スケジュールといたしましては、5月中旬をめどに事業を開始いたしまして、万博開催期間である10月まで継続して実施する予定でございます。
今、目的と概要をお聞きいたしました。観光情報や飲食店の情報をVISAと提携して海外に向けて発信するとのことです。
具体的な事業の流れ、また、その広報というのはどのように行われるのでしょうか。
観光情報などの発信に向け、現在、市町村や観光協会、商工会議所などと連携いたしまして、地域の店舗に参加を呼びかけているところでございます。
店舗は、my door OSAKAの中の専用申請窓口から、店舗名や住所、観光客向けのクーポンの情報などを登録いただくことになっております。
登録された情報は大阪府からVISAに連携され、VISAは海外の会員向けウェブサイトに観光施設や店舗の情報を掲載されます。VISAカードの海外の会員向けメール通知も行うこととなっております。
あわせて、関空のサイネージや南海電鉄などでも広告を掲載し、インバウンドへの周知を図ることとなっております。
クレジットカードのシェアではVISAが50%以上占めているとお聞きしております。海外へのPR効果は高いと期待しておりますので、ぜひともしっかりと取り組んでいただきますようお願いします。
今回は、泉州地域を対象に実施するとのことです。現時点での店舗や観光施設の参加状況についてお聞かせください。
本事業は、VISAのネットワークとデータを活用した新たな周遊施策として、同社でも初の取組であり、参加店舗に対するフォロー等の対応可能な件数といたしましては、50から100店舗を目指して募集を行っているところでございます。
現時点では、約60の店舗や施設が本キャンペーンへの参加を表明いただいております。包丁研ぎの実演を行う店舗や、相撲を鑑賞しながら食事ができるレストランなど、インバウンド向けのサービスが充実した店舗にも参加をいただいており、PR効果は高いものと考えております。
また、このような店舗情報に加えまして、仁徳天皇陵古墳や岸和田城といった各市の主要な観光スポットの情報も、VISAの観光サイトを通じてPRすることとなっております。
インバウンド向けにPR効果の高い店舗や観光施設も参加されているとのことです。大いに期待していいんかなと感じております。
万博の機会にこの事業がなされるということは意義深いことでありますが、スマートシティ戦略部がこれに取り組むということを考えれば、もちろん観光振興も大事ですが、大阪のスマートシティー化推進という観点からも非常に意義があることやと感じております。
本事業でORDENも活用していくとのことです。スマートシティ戦略部として、この事業の結果を今後どう生かしていくのか、こちらも、戦略企画課長、お願いいたします。
本事業を踏まえまして、次の3点を今後の施策に生かしていきたいと考えております。
1つ目は、民間企業との連携でインバウンドに広く府域を周遊してもらうというスキームを実証いたしまして、これを関西広域に広げていきたいというもの。
2つ目は、my door OSAKAを通じまして参加申請を受け付けることで、my door OSAKAの利用者の拡大につなげるとともに、市町村にとっては、独自の受付サイトをわざわざ用意する必要がありませんので、市町村負担が軽減されることになるかなと思っております。My door OSAKAの普及拡大とともに、市町村には導入によるメリットを感じてもらいたいというふうに感じております。
3つ目は、事業実施後に、実施期間におけるインバウンドの決済データをデータ連携基盤のORDENに提供いただけることになっております。この決済データを分析することで、来阪したインバウンドの動向や消費活動を把握し、関係部局と協力しながら、次なる施策やサービスの創出につなげていきたいというふうに考えております。
万博会場、大阪市内だけでなく、今回は泉州地域です。大阪府域のあちこちに目を向けてもらうということは非常に大事なことやと思います。先ほど、周遊観光という話も取り上げましたが、まずは、関係市町村や事業者と連携を図りながら、しっかりとPRに取り組んで、事業を成功させていただきたいと考えます。
また、スマートシティ戦略部がこういうことをやる。データを集める。旅行者がどこへ行って何を買って、どこに泊まったとか、こういうデータを取る。これ、まさにVISAタッチでピッとやってもらったら、VISAはそれを自動的に集めて、それをスマートシティ戦略部がおおきに、データだけをと、こんな強いものはないわけです。
このデータは、素人が見ても分からへんですけど、多分、プロが見たら宝の山なんやと思います。これをどれだけORDENに集められるかというのも非常に大事なことやと思います。どこまでVISAからデータを提供してもらえるのか、どういうレベルのデータなのか、そこはしっかりとまたVISAとも調整していただいて、ぜひとも、こちらとしても、ORDENをつくった値打ちのあるものになるように、さすがやなと思ってもらえるように頑張っていただければと思います。
2025年3月12日
●スーパーシティー
それでは、最後の質問です。スーパーシティーについてお伺いいたします。
スーパーシティーは、大阪・関西万博をマイルストーンとして、夢洲とうめきた2期地区で、先行的、集中的にプロジェクトが進められてきました。この両地区は、いずれも開発時点で人が住んでいないものの、新たな都市開発を進めることでにぎわいを創出する、いわゆるグリーンフィールドであります。
内閣府のホームページを見ますと、スーパーシティーとは、住民が参画し、住民目線で、生活全般にまたがる複数分野の先端的サービスの提供などを目指すこととされております。住民や生活に根づいたものであるべきと私も考えます。
そこで、私の地元ですが、新大阪駅周辺地域というのが令和4(2022)年10月に都市再生緊急整備地域という指定を受けました。北陸新幹線やリニア中央新幹線の全線開業、そしてまた、先日決まりましたキャッチコピーの「新しいの、その先へ 新大阪」というまちづくりの検討が進んでおります。
私も、この地域の皆さんと、私自身も一地域住民ですが、あれこれ、このまちをどうしたらいいかなとか、お話を聞いている中で、住民目線での地域の課題解決にスーパーシティーというのが使えるんやないかと、お話を聞いてて感じた次第です。
グリーンフィールドだけでなく、住民の皆さんが暮らすいわゆるブラウンフィールドこそ、スーパーシティーという道具立てが使える本領発揮の場所やないかなと思った次第です。
今後、新大阪のように、大規模開発が進み、かつ、既に多くの住民の方が住まれているような地域でこそ、スーパーシティーの展開を図っていくことで、他の都市にない、さすが大阪と言われるまちづくりのモデルを全国的に発信できるんやないかと思います。
今後、新たなスーパーシティーの展開に向けた仕組みを検討されるとのことです。この仕組みが、どのように、人々が暮らすブラウンフィールドでも取組が広がっていくことに結びついていくのでしょうか、特区推進課長、お願いいたします。
お答えします。
今後のスーパーシティーにつきましては、夢洲、うめきた2期での現在の取組、これの継続はもとより、いわゆるグリーンフィールドやブラウンフィールドという枠にとらわれない、そして、変化の速い先端的サービスにも対応可能な柔軟でスピード感ある展開が重要、このように認識しております。
このため、来(2025)年度、地域や企業等から広く提案を募りまして、このうちから、一定の要件を満たすものをそれぞれ選定しまして、選定した地域、選定した企業等とのマッチングですとか、これら地域、企業におけるORDENなどデータ連携基盤の活用、規制改革提案などに係る支援を、大阪府、大阪市が連携して行う、こうした一気通貫の仕組みを、実地でのモデル的実証も含めて検討させていただきたいと考えているところでございます。
このように、幅広く様々な地域、企業などが新たなスーパーシティーの取組をしたいと提案し、実際に参画できる仕組みを導入していくことで、ブラウンフィールドとされる地域においてもスーパーシティーの展開ができるようにつなげていきたいと考えております。
私自身、この質問をするに当たって、改めて、大阪市全体がスーパーシティーの区域指定を受けているということに気がつかされまして、すいません、ほんまにお恥ずかしい限りですが、なんや、そうやったら、うちの地域も可能性があるやんと大いに期待を寄せているところです。
私の頭で思いつくようなことはたかが知れていますが、本当にいろんな知恵をいただいて、これは、ここを突いたら本当にすごいことができるよなという、そのためのスーパーシティーという道具立てで、せっかく、皆さん、大阪府、大阪市挙げて取りに行って取ってきた仕組みですので、うまく最大限生かせるように、こちらもまた地元の皆さんとも意見交換しながら、知恵を絞っていきたいと思います。
最後に、この年度末で御卒業される課長以上の職員さんはいらっしゃいますかと、いろいろお聞きしましたら、おなじみ坪田部長と、あと、府民文化部の岡本消費センター所長やとお聞きしております。ほかに、もし課長以上の方でいらっしゃったら申し訳ないんですが、こちらがお聞きしたところ、そのお二方でございます。
このお二方に関しましては、ほんとに、これまで府政に御貢献いただきましたことに感謝を申し上げますとともに、4月からまた恐らく新たな舞台での活躍が4月すぐか、ひょっとしてちょっと空いてからか分かりませんが、新年度また新たな舞台で御活躍をされることと期待しております。大阪府のためにも、またお力をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で私の質問を終わります。