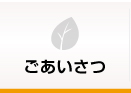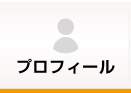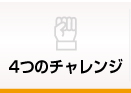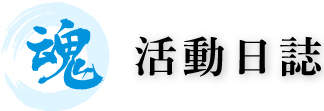第5期
2026年
2025年
2024年
2023年
第4期
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
第3期
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
第2期
2014年
2013年
2012年
2011年
第1期
リニア中央新幹線建設促進期成同盟会総会に出席
5月28日(水) 晴れ
東京都内のホテルで開かれたリニア中央新幹線建設促進期成同盟会の総会に出席しました。(写真)
リニア中央新幹線沿線自治体の知事や国会議員らがあいさつ、東京―名古屋間だけでなく大阪までの早期全線開業や、建設工事の途中で起きる事故への丁寧な対応などを訴えていました。
リニア新幹線の大阪のターミナル駅がどこにできるかは現時点で未定です。総会決議には「周辺地域のまちづくりの推進のためにも早期に確定するとともに、既存の新幹線や在来線との乗換等の利用者利便性を考慮すること」とあります。新大阪駅を地元に抱える議員として、早期の駅位置確定を訴えていきます。

写真
ギャンブル依存症対策シンポジウムに出席
5月25日(日) 晴れ
全国ギャンブル依存症家族の会大阪と(公社)ギャンブル依存症問題を考える会共催の「広がるオンラインカジノ 迫る大阪IR 進めよう依存症対策!」と題した特別セミナーに公明党大阪府議会議員団を代表し、パネリストとして出席しました。(写真1、2)
第1部は考える会代表の田中紀子代表が講演、若いうちからギャンブルを始めると依存症リスクが高くなることや、ギャンブル産業には若者をターゲットとする広告をやめてほしい、などと訴えました。
また、関西学院大学の上村敏之教授が登場し、自身の教え子だった女性や田中さんと大学生への依存症予防教育について話し合いました。「後輩たちの未来を守りたい」と母校へ出かけて予防教育をする取り組みも始めています。同世代の人から聞くことで学生もより現実味を感じてくれるのではないでしょうか。
第2部は私をはじめ府議会議員6人によるシンポジウムです。今現在、切実に困っている人たちにしてみれば一刻も早くギャンブル等依存症対策を強化してほしい、というのが痛切な願いでしょう。壇上にいて私も痛感しました。
府は「大阪依存症センター(仮称)」を2030年秋のIR開業までには発足させる、として検討を進めています。ワンストップでの相談窓口となる同センターの早期実現を働きかけていきます。

写真1

写真2
府立大阪わかば高校を視察
5月16日(金) 晴れ
大阪府立大阪わかば高校(大阪市生野区)を大竹いずみ府議(吹田市選出)と一緒に訪れました。(写真1)
多部制単位制の同高校は2022年から日本語指導の必要な外国ルーツの生徒を受け入れています。全校生徒475人のうち外国ルーツの生徒は175人、うち139人が日本語指導の必要な生徒だそうで、人数は毎年増える一方です。
また、日本で義務教育を受けていない、受けていても1年以内の生徒が増え、一から日本語を教えなければならない状況が起きています。やさしい日本語を使った授業や日本語そのものを学ぶ授業を展開しています。
2024年度からは教員による「多文化共生・日本語チーム」をつくり、生徒の学校生活を多面的に支援しています。特に日本語を教える教員は「大阪わかば高校で働きたい」とやってきた人もいるとのことです。
この日は順に1年生の「日本語リテラシー」、3年生の「日本語コミュニケーション演習」、2年生の「日本語実践」の授業にお邪魔しました。
1年生の授業は日本語の能力に応じてクラス分けされています。日本の昔話や学校生活の様子など簡単な日本語で書かれた本を多く読むことで語彙数を増やすのが狙いだそうです。(写真2)
3年生の授業にはこの春卒業して就職した先輩が自らの体験を話しに来てくれていました(写真3)。勤務先の会社からも「よくがんばってくれています」とお褒めの言葉が学校にあったそうです。
2年生の授業には生野区で活動するNPOの人たちが来ていました。名刺交換を実体験してもらう、ということで私も仲間に入れてもらいました。(写真4)
2028年度からは日本語教育に関し府立高校の「拠点校」となります。外国ルーツの生徒のための日本語指導だけでなく進路相談などで他校を支援する役割が求められています。「複数のことばと文化を持つ可能性のある子ども」をどう育てていくのか、同高校の挑戦を注目しています。

写真1

写真2

写真3

写真4
関西国際空港を視察
5月15日(木) 晴れ
第1旅客ターミナルビルの大規模改修工事が一段落した関西国際空港を約2年半ぶりに視察しました。(写真1)
4階にある国際線の保安検査場が時間当たりの処理人数を増やしたり、入国審査場は3階に移設して拡張したりと旅客数の増加に対応しています。また、ファースト、ビジネスクラス旅客向けのラウンジを1か所に集約、より広い空間を提供しています。
この先、国際線出発エリアで壁の向こう側に商業施設を増やし、2026年夏の完成を見込んでいます(写真2)。既存の施設を運用しながらの改修でしたが、着工した2021年5月は新型コロナ禍で旅客数が大きく落ち込んでいたため大きな混乱はなかったといいます。天の時をうまく味方につけた、ということでしょう。
1994年9月の開港から30年が過ぎ、海外に向けた大阪・関西の空の玄関口としての役割はますます重要になってきます。就航都市の増加など機能強化を進めていきます。
おまけの1枚。1階到着ロビーから見えるよう、大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」の垂れ幕が大きく下がっていました。(写真3)

写真1

写真2

写真3
北陸新幹線建設促進大会に出席
5月12日(月) くもり
東京都内のホテルで開かれた北陸新幹線建設促進大会に出席しました。(写真)
北陸新幹線は2024年3月、金沢駅(石川県金沢市)から敦賀駅(福井県敦賀市)まで延伸され、敦賀駅から新大阪駅までの区間が未開業のままです。
敦賀駅から新大阪駅までは福井県小浜市や京都市などを通る「小浜―京都ルート」で建設の準備が進んでいます。ところが、着工の見通しが立っていないため、石川県は24年7月「北陸新幹線建設促進石川県民会議」でルート再検討などを求める決議を採択しました。
この日の大会で馳浩・石川県知事が県民会議の決議の趣旨などを説明。小浜―京都ルートを求める大会決議には賛成するが、そのためにも京都府内の着工に向けた課題解決の環境整備をしてほしい、と訴えました。
大会決議の採択前には石川県の出席者が知事や県議会議長ら少数を残して退席したあたりに県のつらい立場を垣間見た気がしました。
北陸新幹線を米原駅(滋賀県米原市)へ延伸する場合、滋賀県の同意が必要となります。関西広域連合長として大会に出席していた三日月大造同県知事は「米原ルートを望んでも求めてもいない」と強く否定しただけにこちらも困難が立ちはだかります。
敦賀―新大阪間は大半がトンネルで、新大阪駅も地下駅となります。難工事が予想されるだけに、沿線地域の理解と課題克服に向けた関係者の努力が不可欠です。大阪でもできることをしないといけませんね。

写真
府立布施北高校を視察
5月8日(木) 晴れ
山下浩昭府議(東大阪市選出)と一緒に府立布施北高校(東大阪市)を訪れました。(写真1)
布施北高校は2005年度から府立高校で現在8校ある「日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜」実施校(枠校)の1校になっています。
本来、1学年で最大16人の受け入れ枠に対し、今年4月の新入生で日本語指導が必要な生徒は31人いるとのことです。2次募集などで後から入ってきたためこのようなことが起きています。
この日は1年生の理科入門と3年生の地理総合の授業を見せてもらいました。1年生の授業では教員がパソコンに日本語で入力すると各国語に翻訳して黒板に表示する仕組みを使い、生徒の理解を手助けしています。非常に便利ですね。(写真2)
3年生の授業は世界各地の時差をどうやって計算するかを教えていました。お互いに人間関係が十分できているからでしょうか、わいわい和やかな雰囲気で授業が進んでいました。(写真3)
布施北高校は「エンパワメントスクール」のため、1年生は英語、数学、国語の3教科は1日30分ずつ毎日授業があります。中学生レベルの課題から学びなおすため、この点は日本語指導の必要な生徒たちにも役立っているそうです。
学校外での活動の一つとして同校のネパールにルーツのある生徒たちが大阪府立中央図書館(東大阪市)所蔵のネパール語の絵本にイラスト付きの紹介文を寄せる、ということもしています。生徒たちの能力を生かすという点で非常にすばらしいことと感じます。
おまけの1枚は「学校蝶」。卒業生からの寄贈品とのことです。(写真4)

写真1

写真2

写真3

写真4
府立東淀川高校を視察
5月1日(木) 晴れ
私の地元にある府立東淀川高校(大阪市淀川区)にお邪魔しました。
東淀川高校は府立高校で8校ある「日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜」実施校(枠校)の1校です。2017年度から受け入れを始め、この4月も中国、台湾、ネパール、フィリピンにルーツのある16人が入学しました。
この入試で合格した生徒を東淀川高校は「くろーばぁ生」の愛称で呼んでいます。四つ葉のクローバーに合わせ「知」「絆」「技」「夢」の4つのゴールを掲げます。それぞれ①日本語学習・教科学習②人間関係(他の生徒との交流・共同作業)③ルーツを学び、第一言語を強みに(母語の力・母語の文化の発信)④夢に向かって羽ばたくための3年間、という意味があります。
この日は3年生の「時事日本語B」(写真1)、1年生の「保健」(写真2)、2年生の「論理国語(日本語)」(写真3、4)などを見せてもらいました。
時事日本語Bは大学受験を想定し、生徒同士が面接官と志願者に分かれて練習をしていました。お互いに日本語が完璧でないからこそ失敗を怖がらずにできる、と授業の狙いをお聞きしました。
保健の授業は生徒の理解を助けるべく、漢字にすべて読み仮名がふってありました。この後、日本人の死因上位であるがんや心臓病、脳卒中を答えさせる場面では英語で病名を書き加えてもいました。
論理国語は生徒の理解度に合わせ2クラスに分かれていました。日本語の文法を学ぶクラスと擬音語、擬態語を学ぶクラスです。どちらも日本語の理解を深めるうえで大切な項目です。
授業の合間や終了後に校長先生らと意見交換をしました。毎回お邪魔するたびに多くの課題を気づかせてもらいます。高校生活の3年間は生徒にとってその後の進路を開くうえでかけがえのない貴重な時間です。こちらも課題解決に引き続き知恵を絞っていきます。

写真1

写真2

写真3

写真4